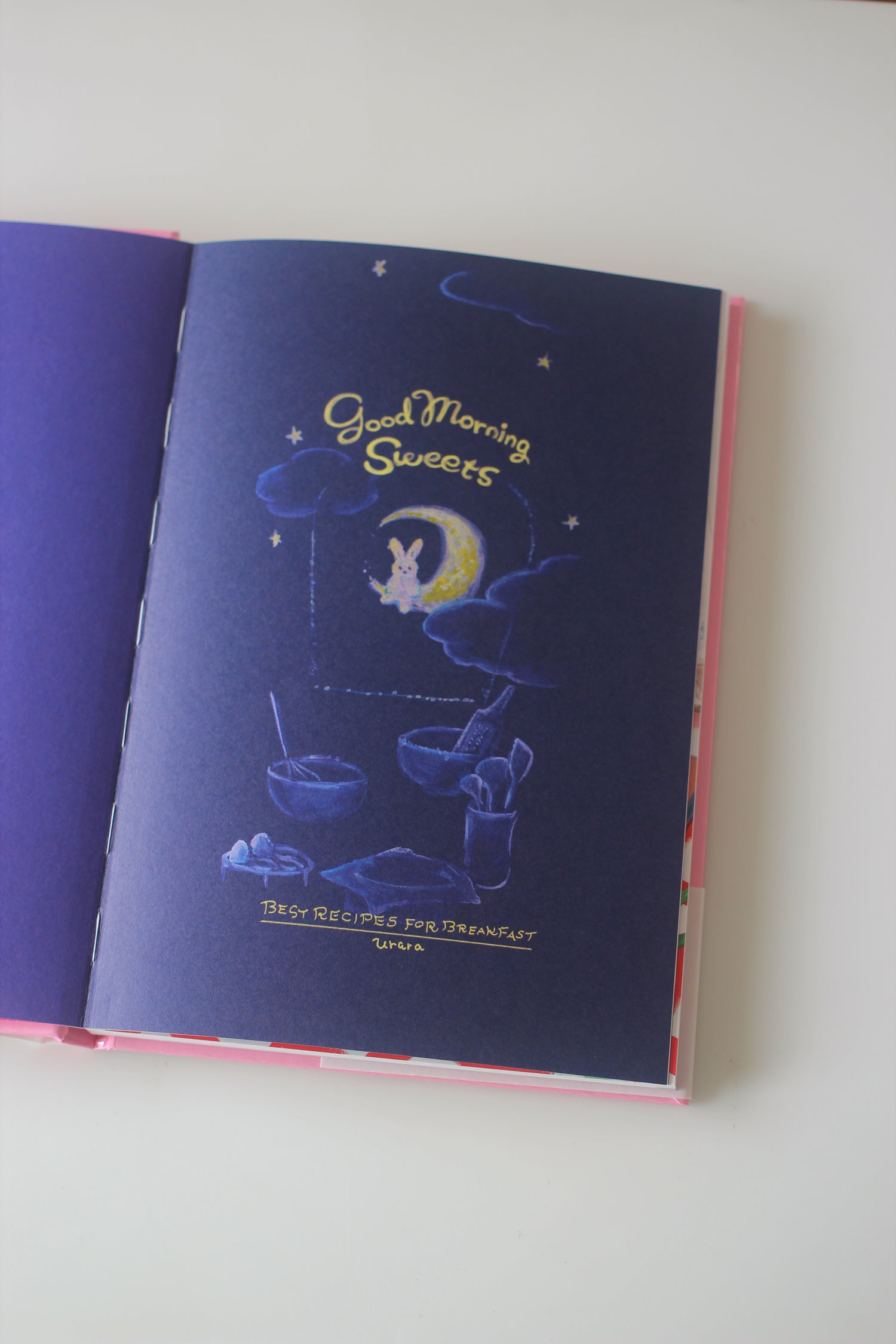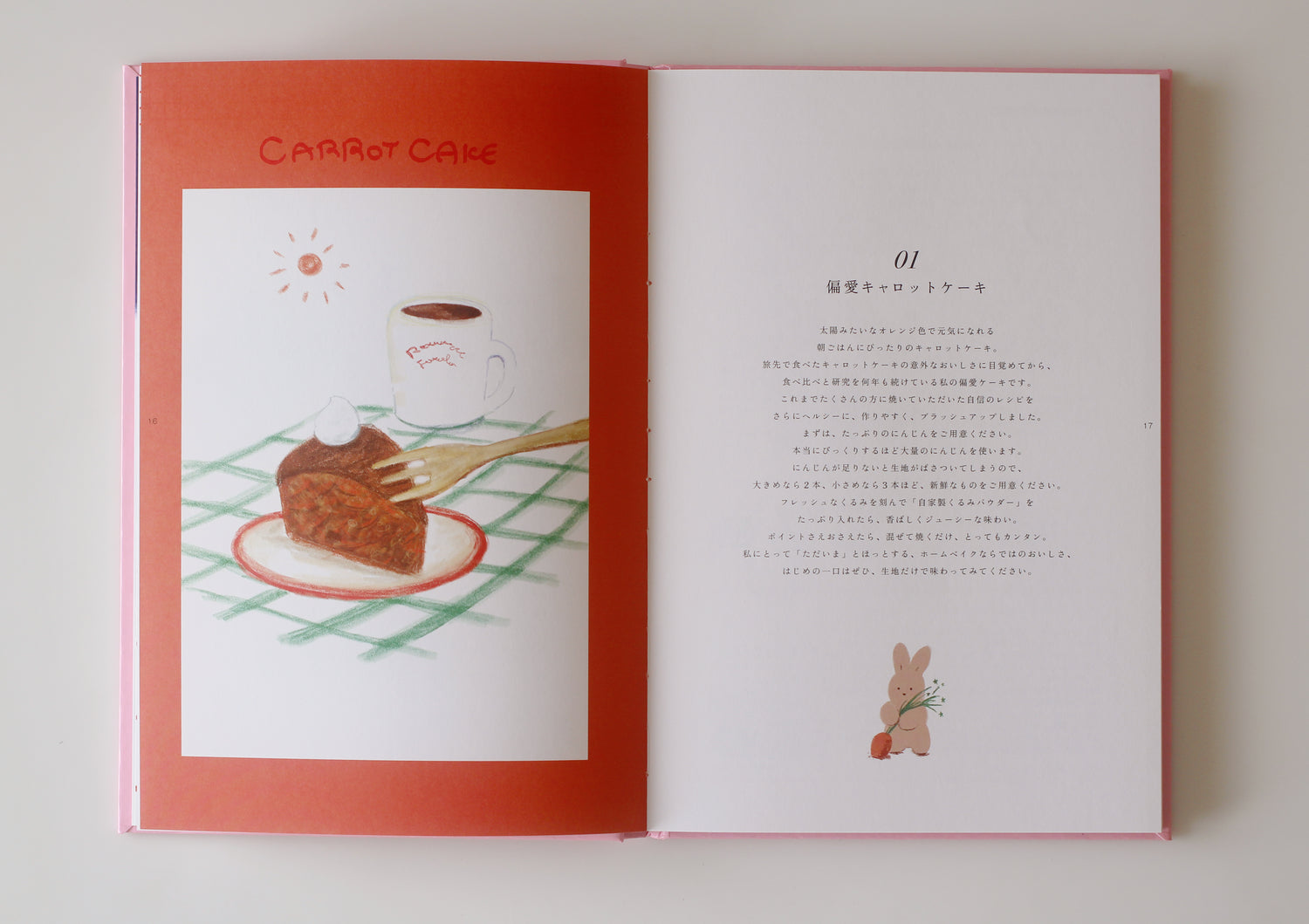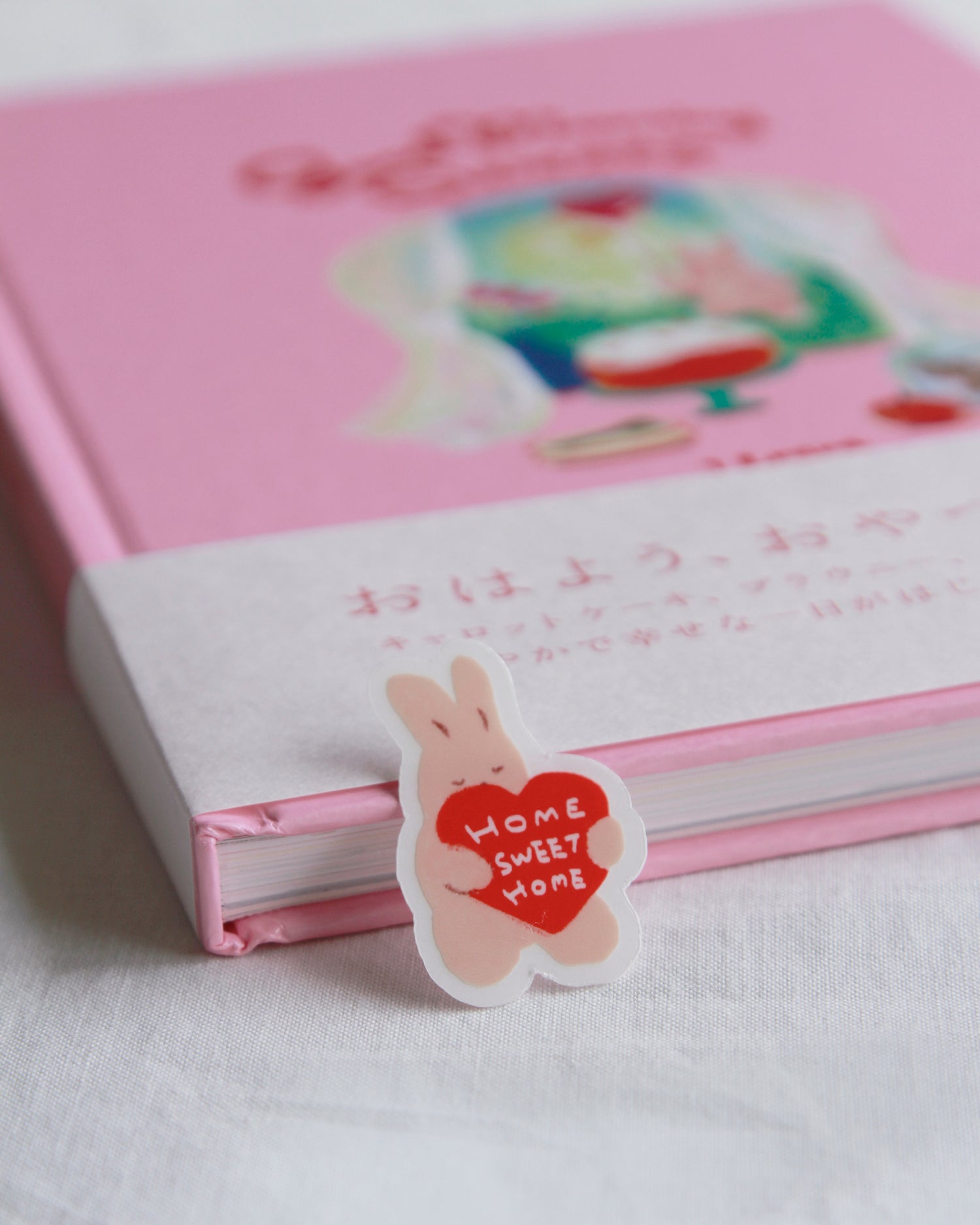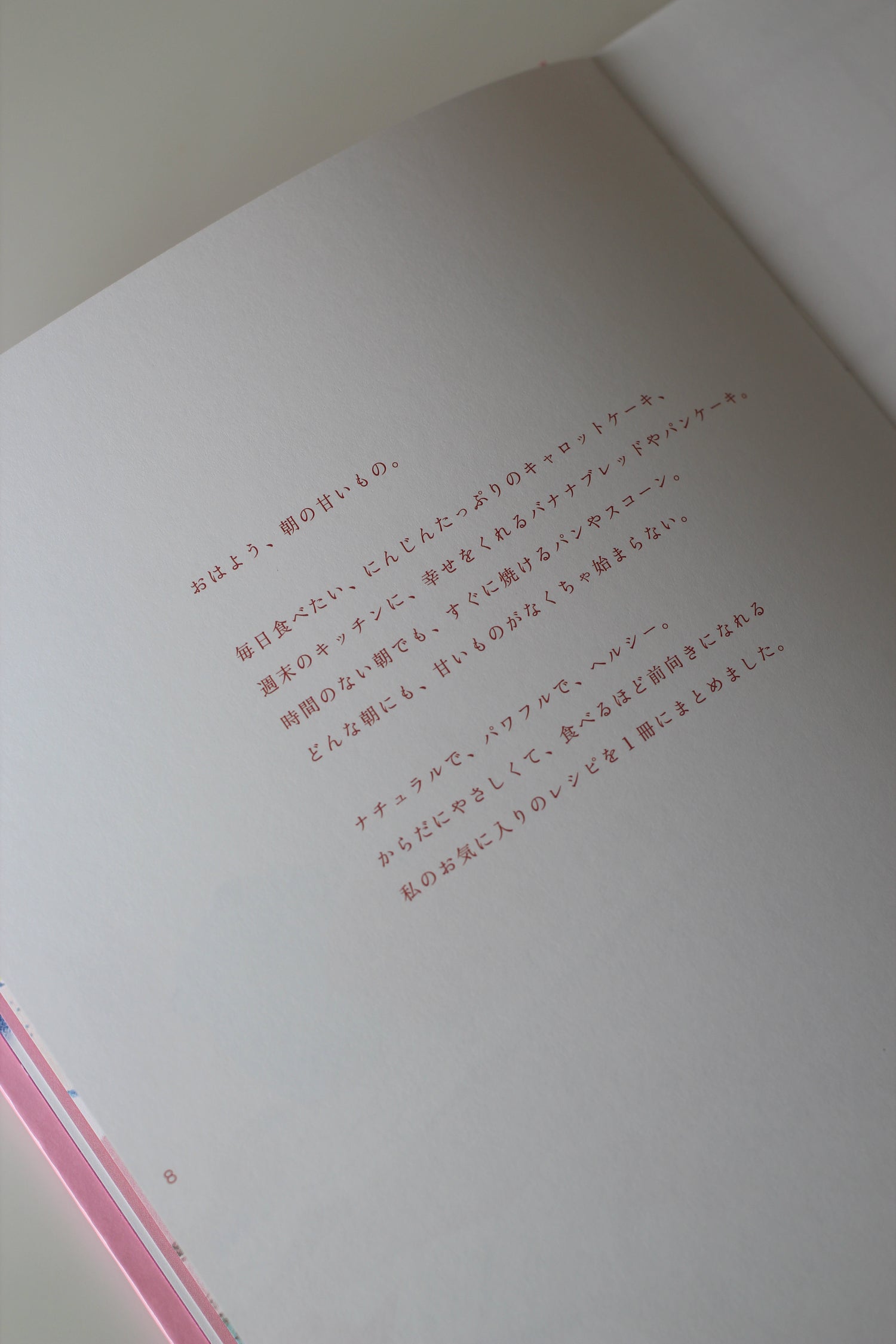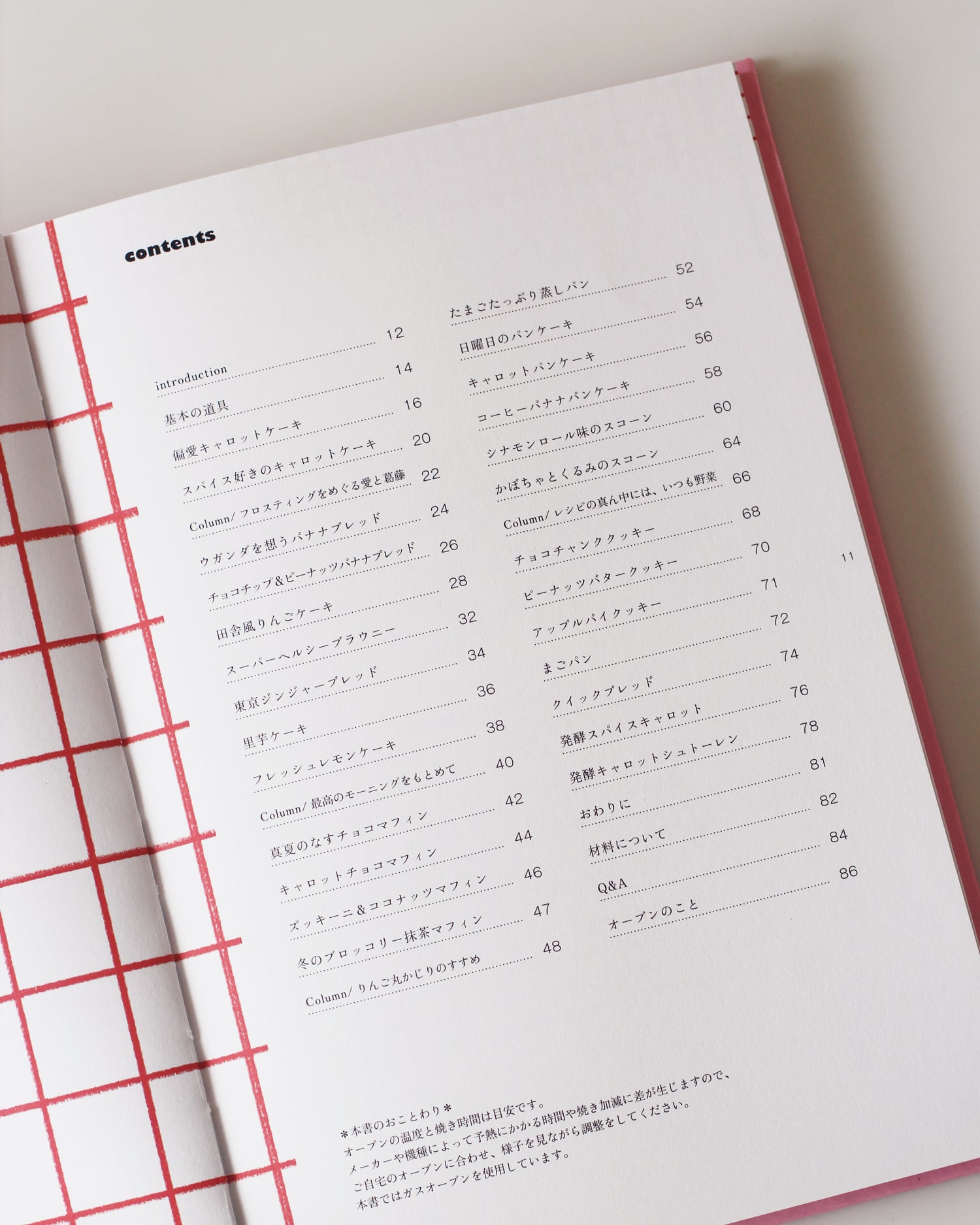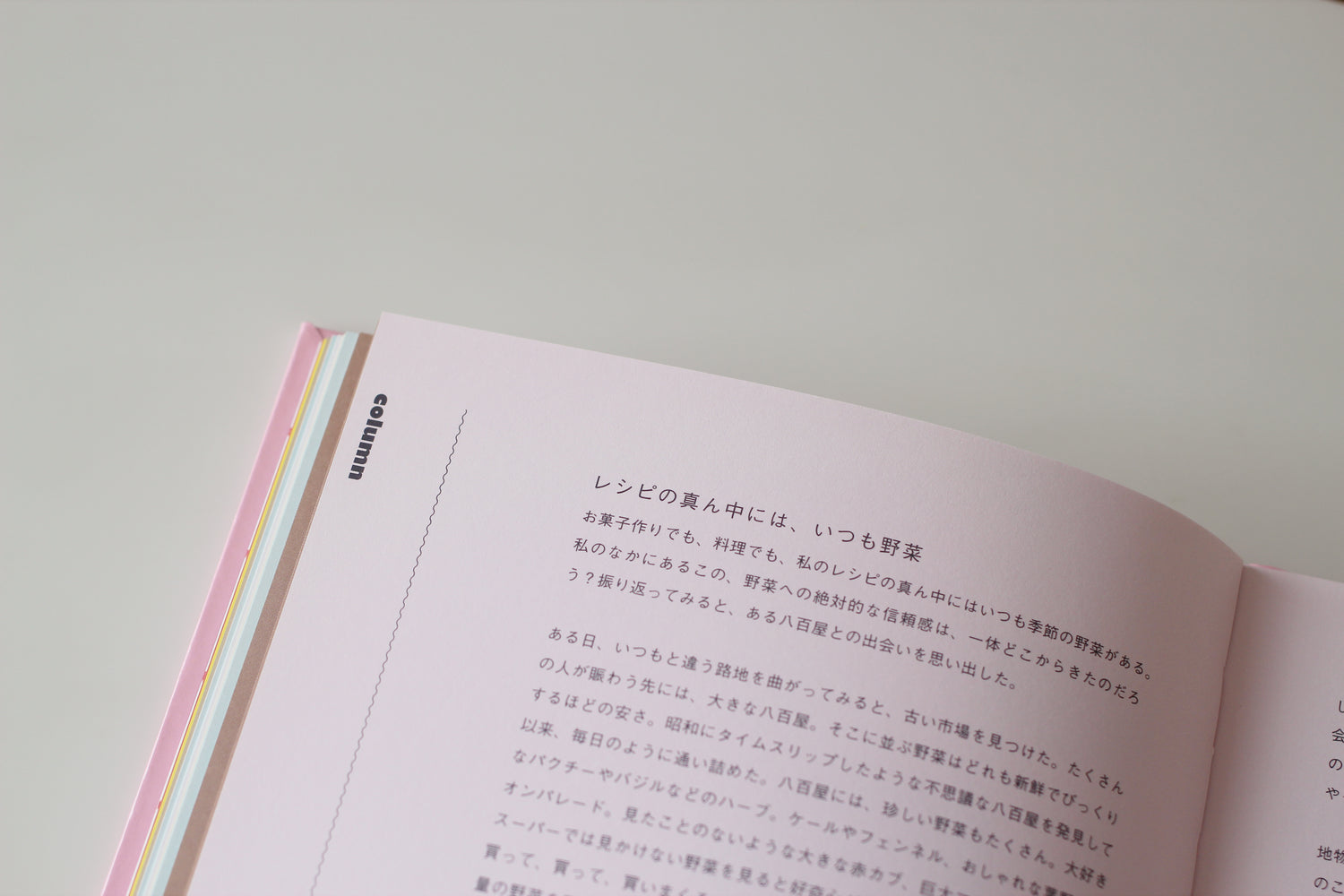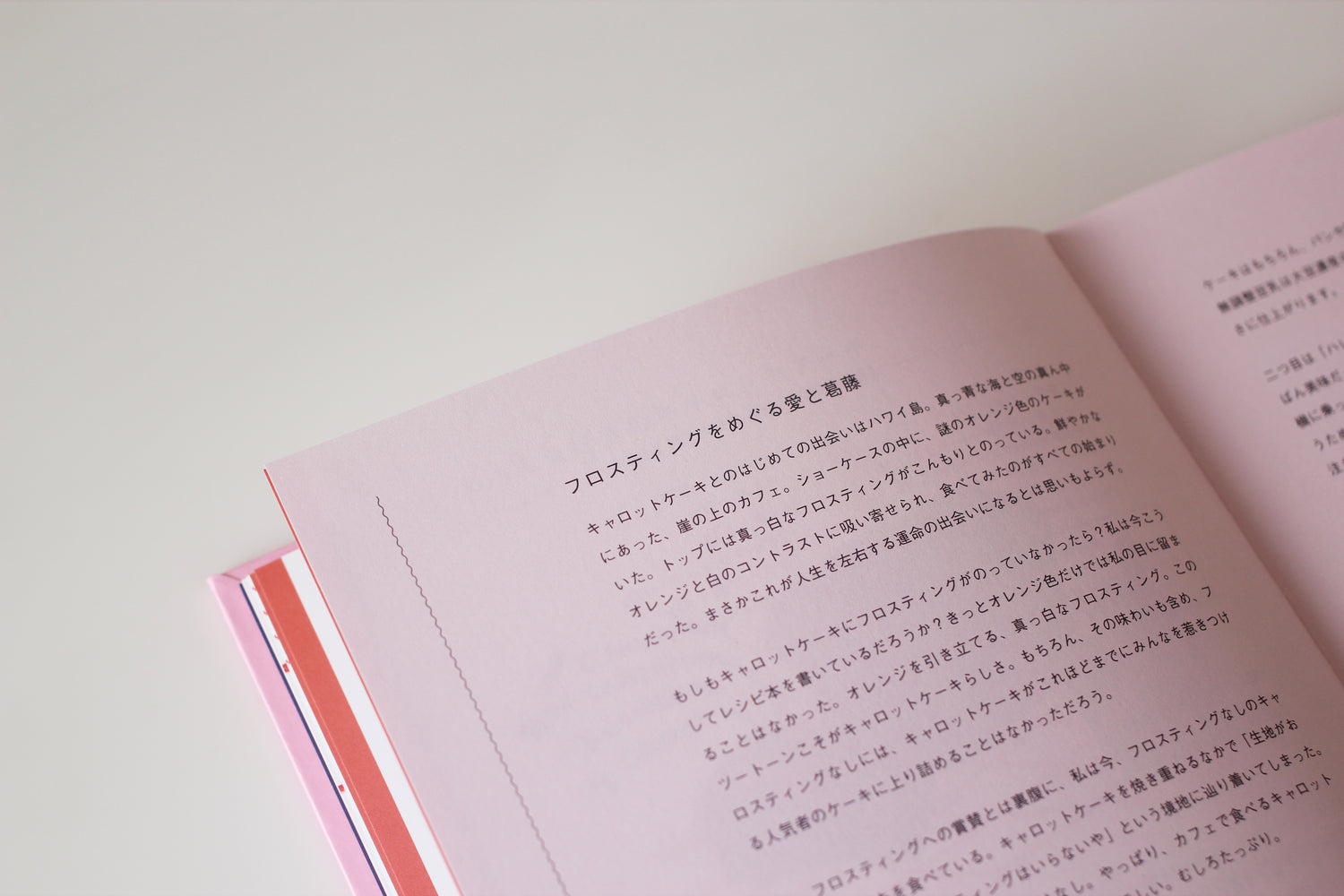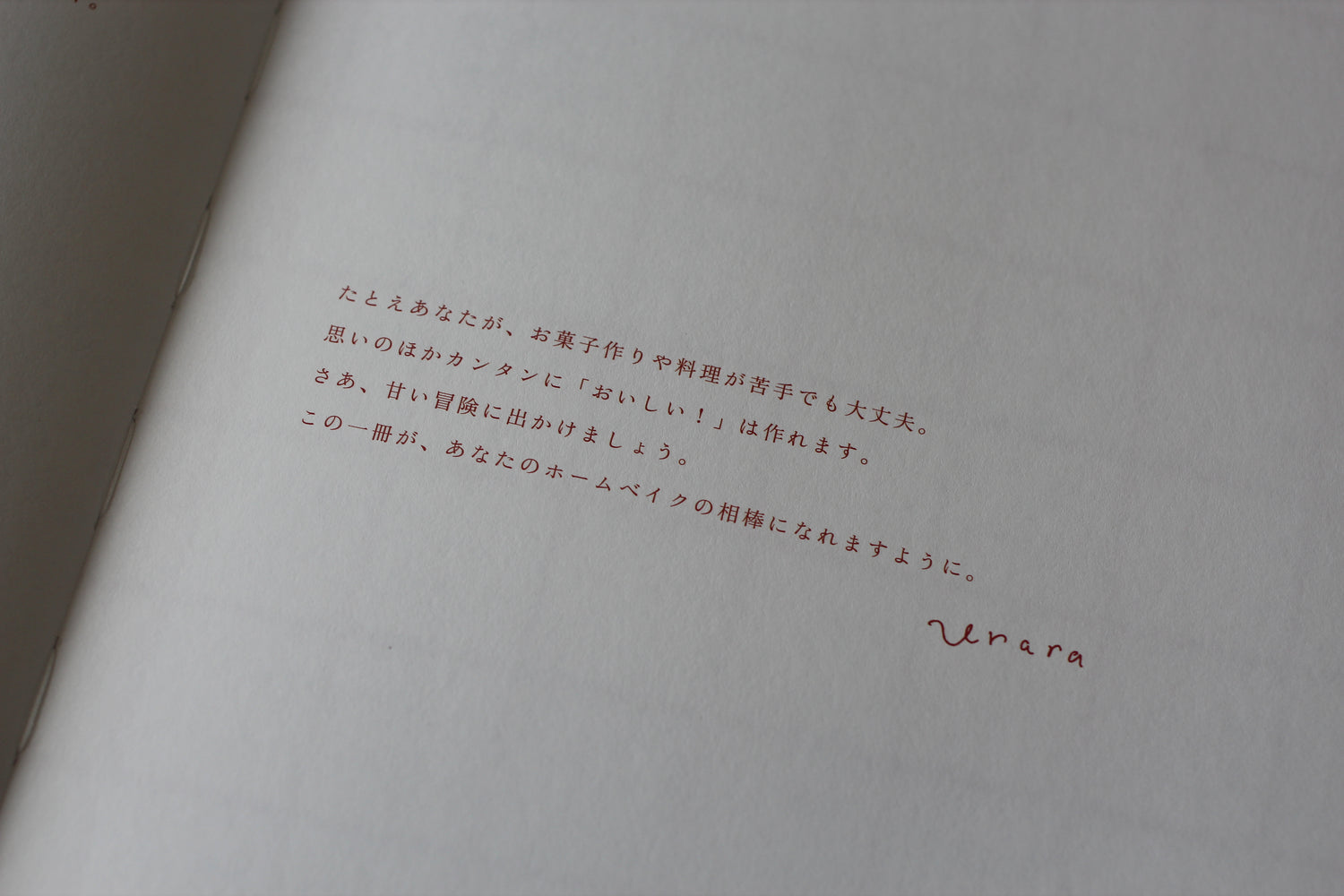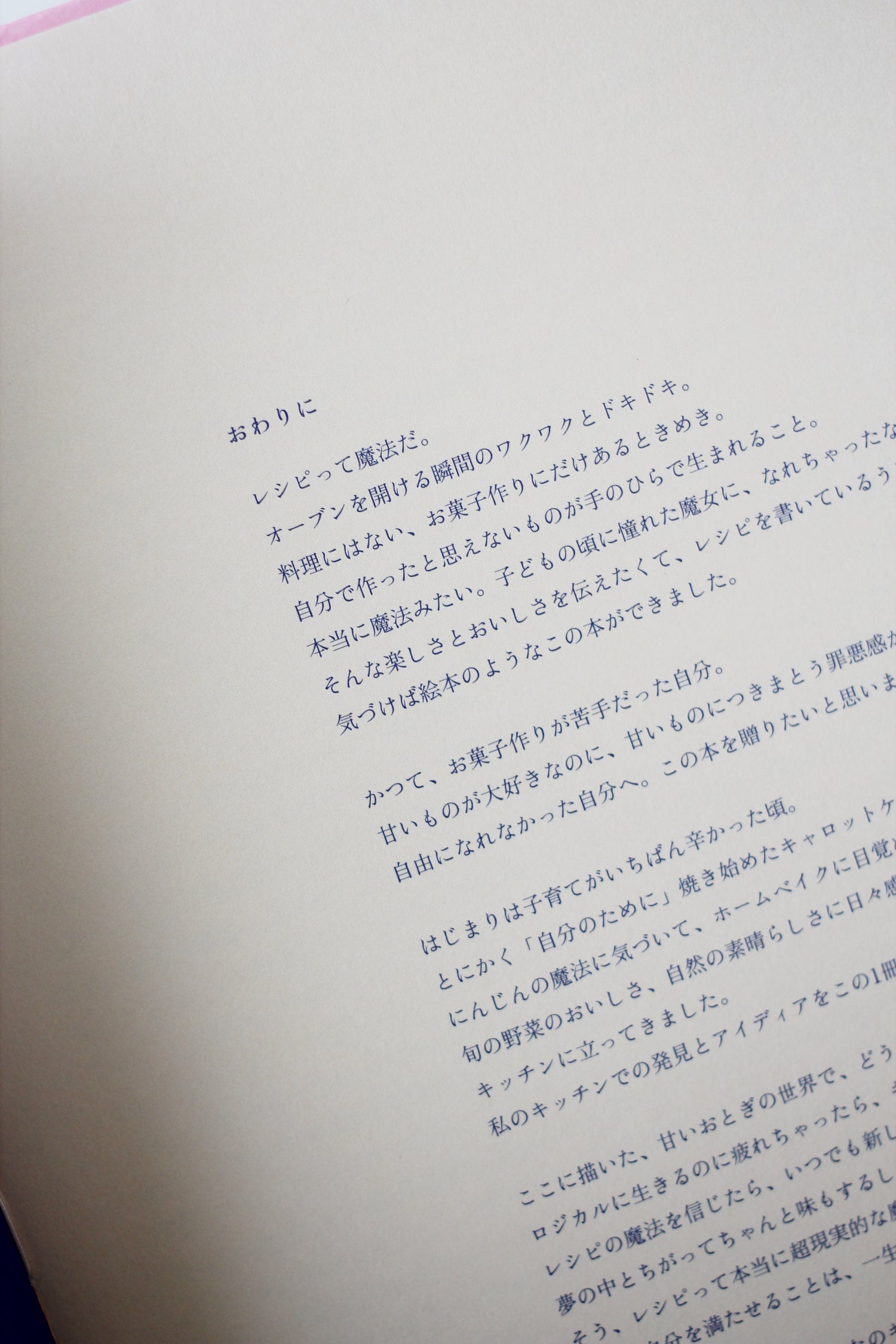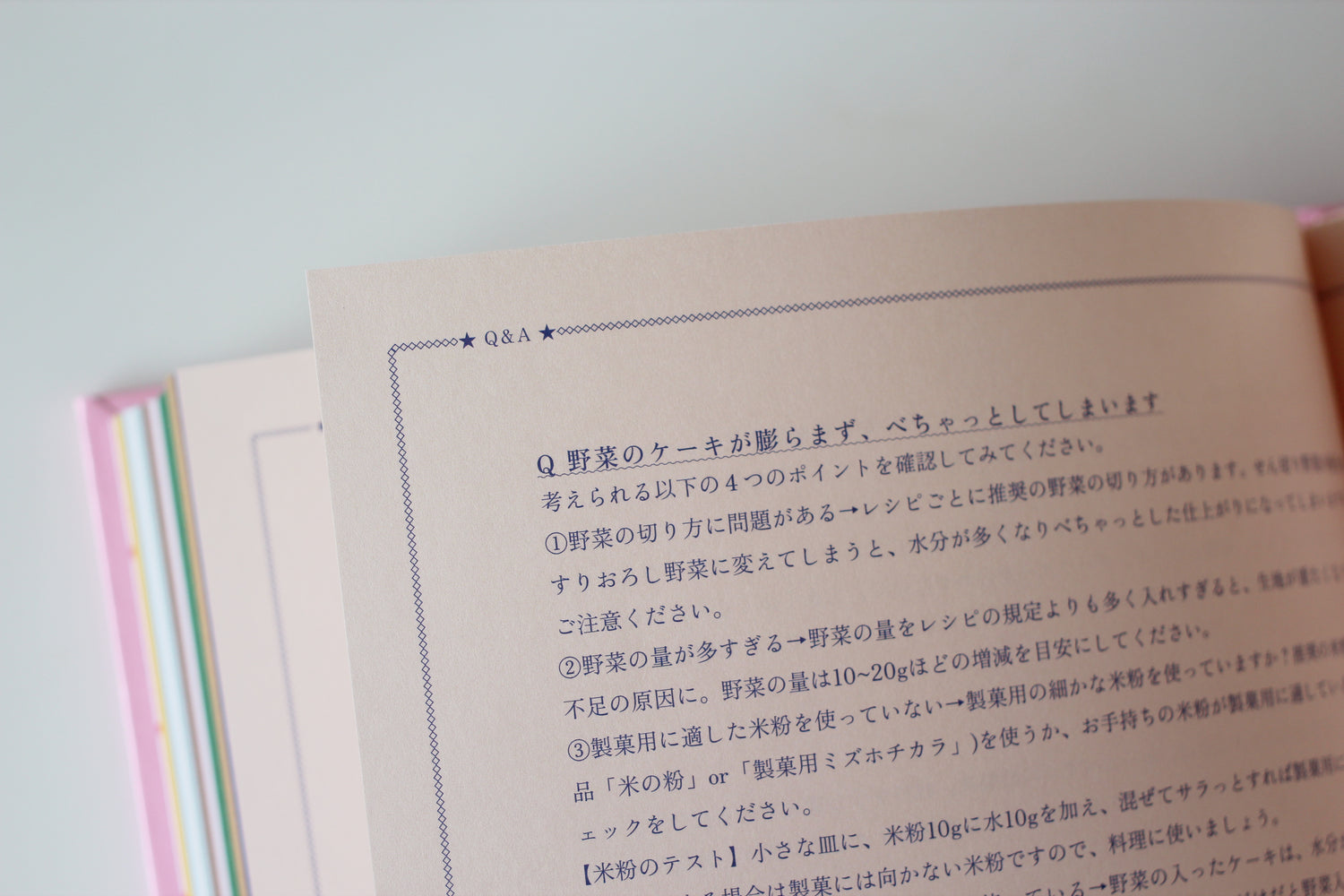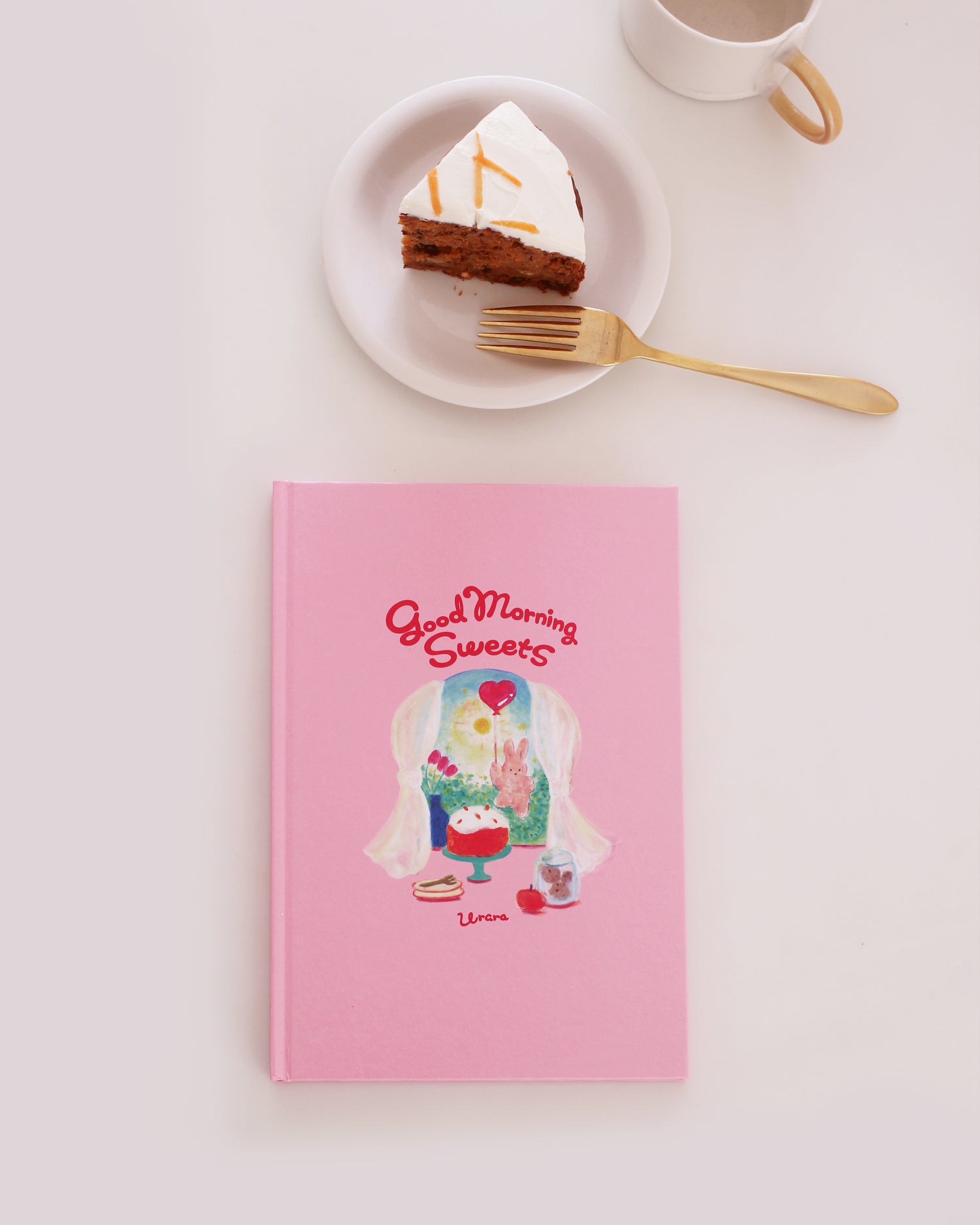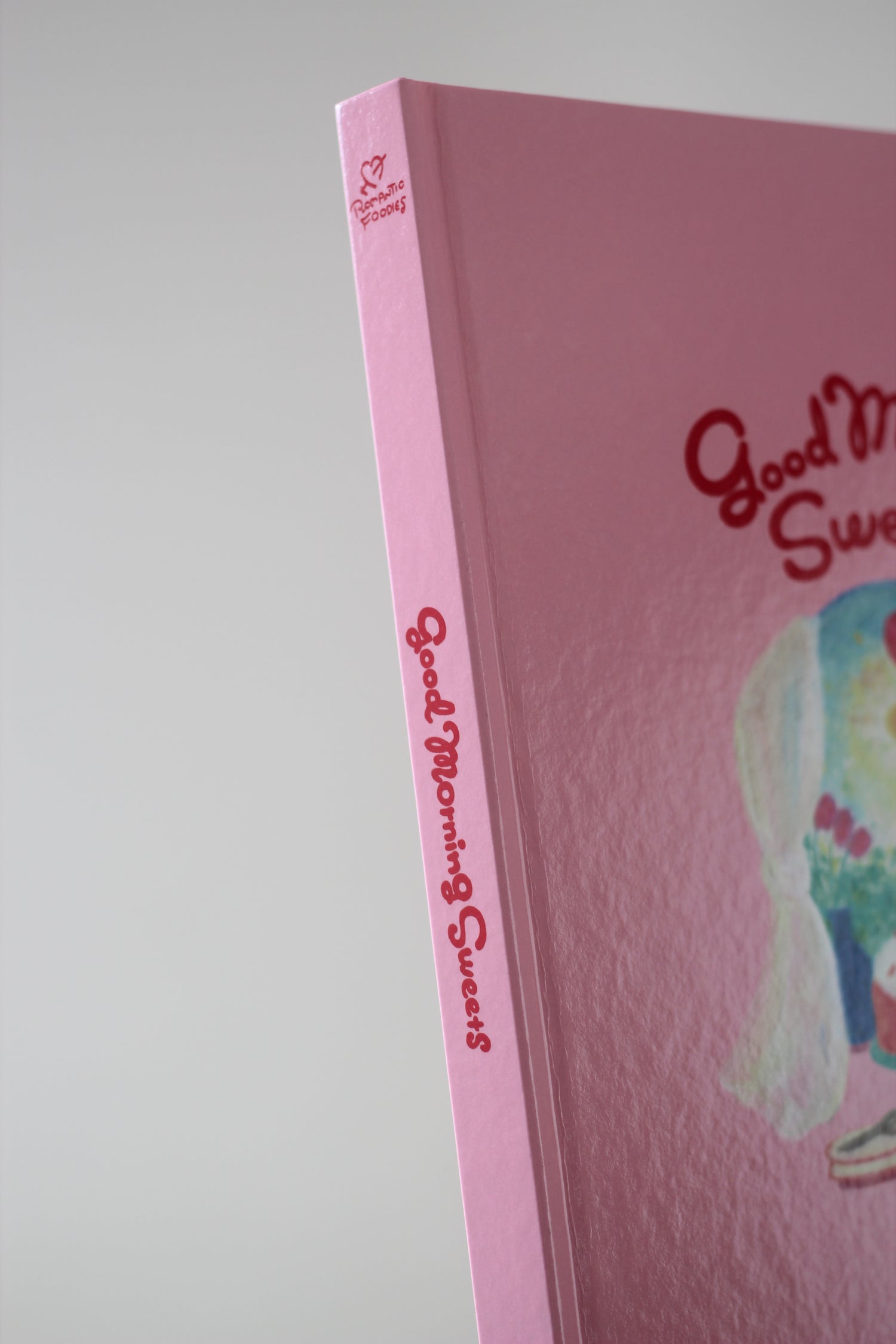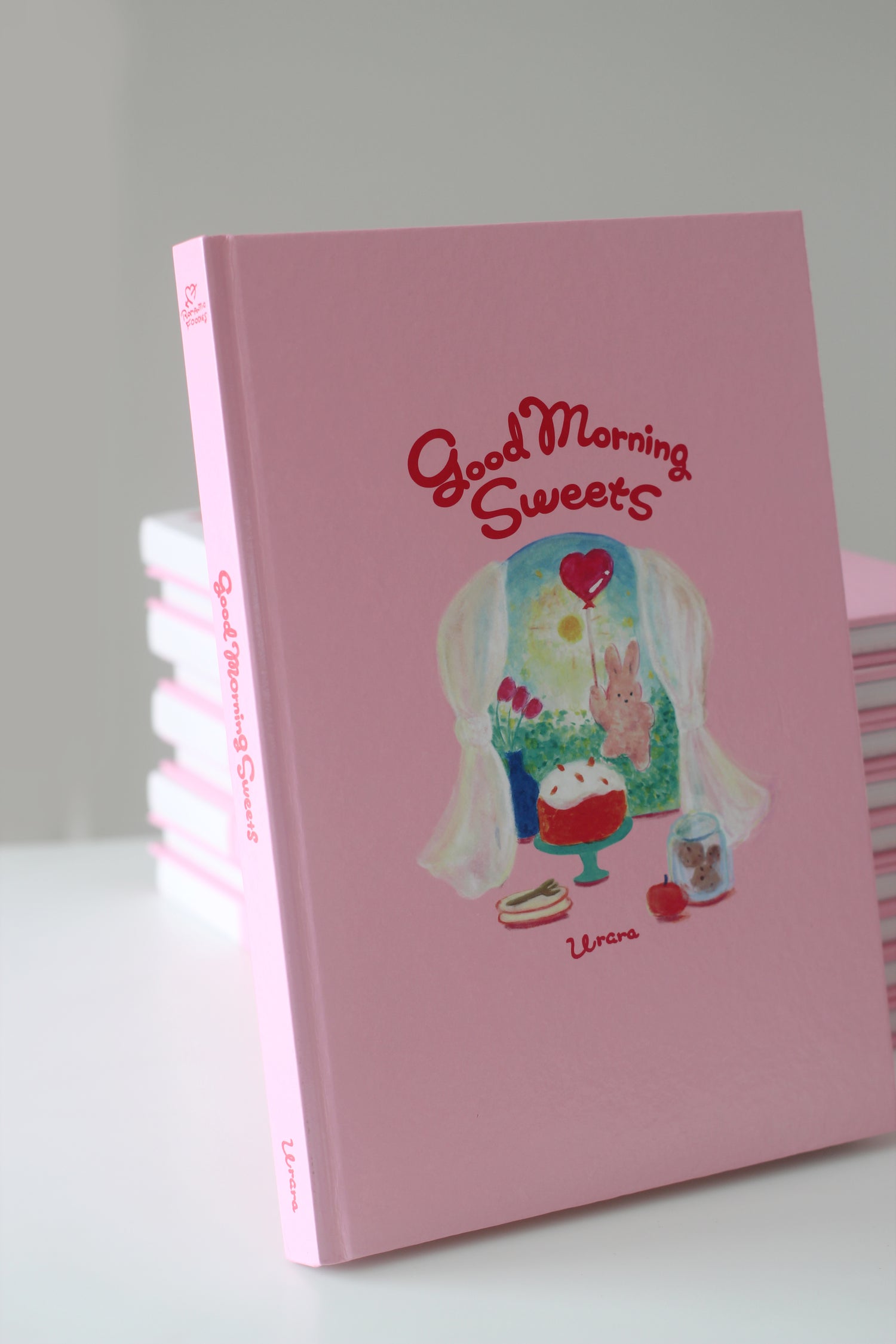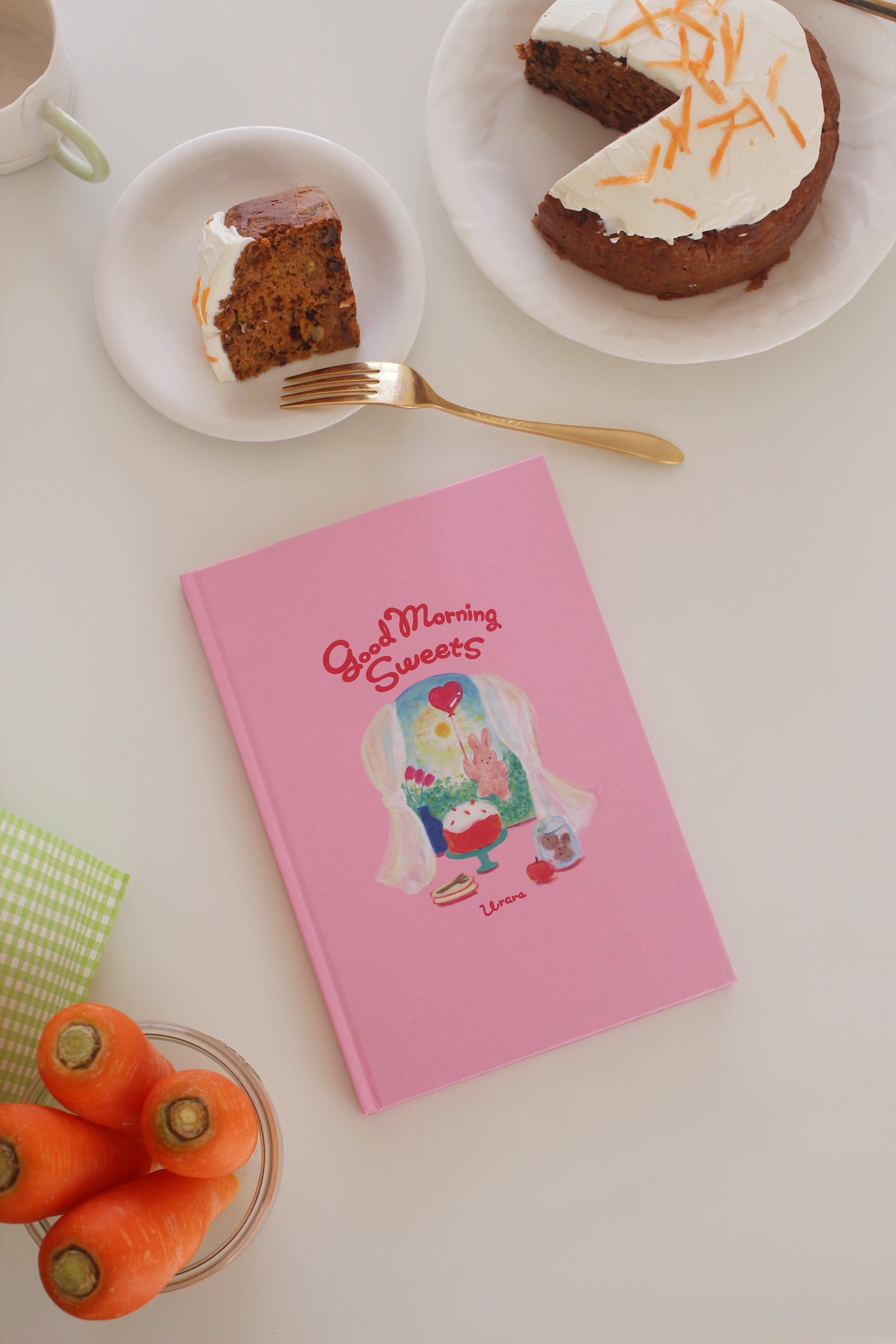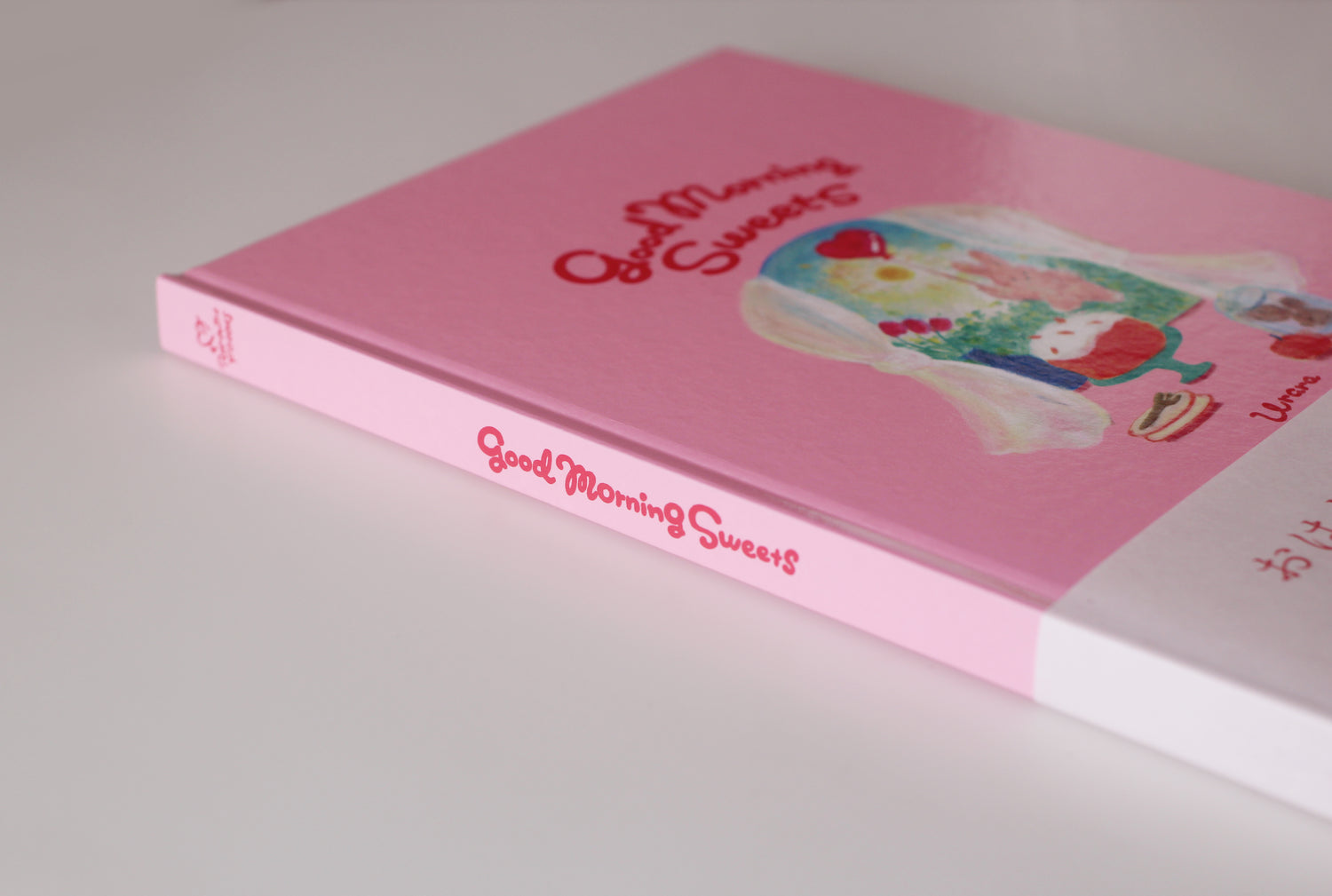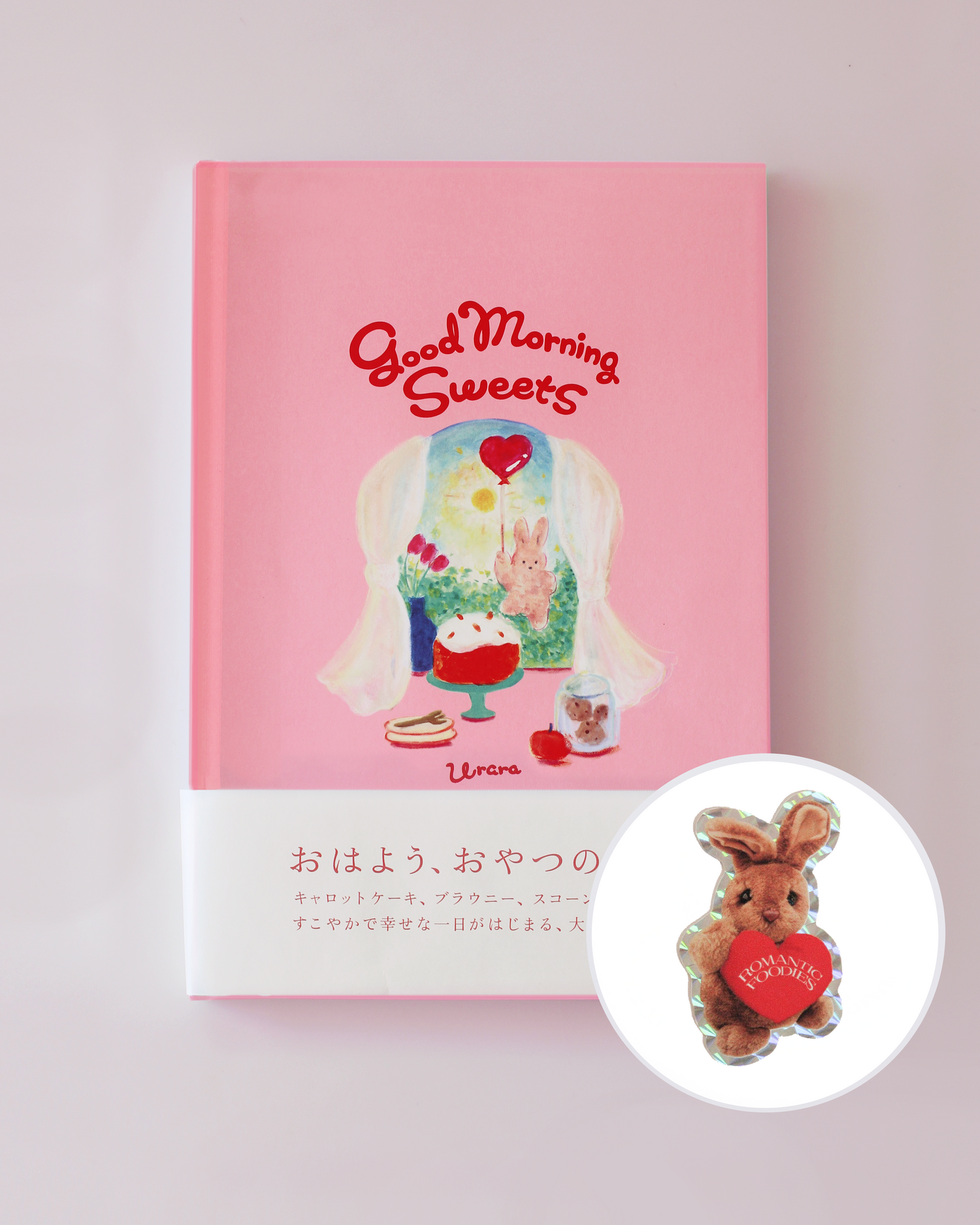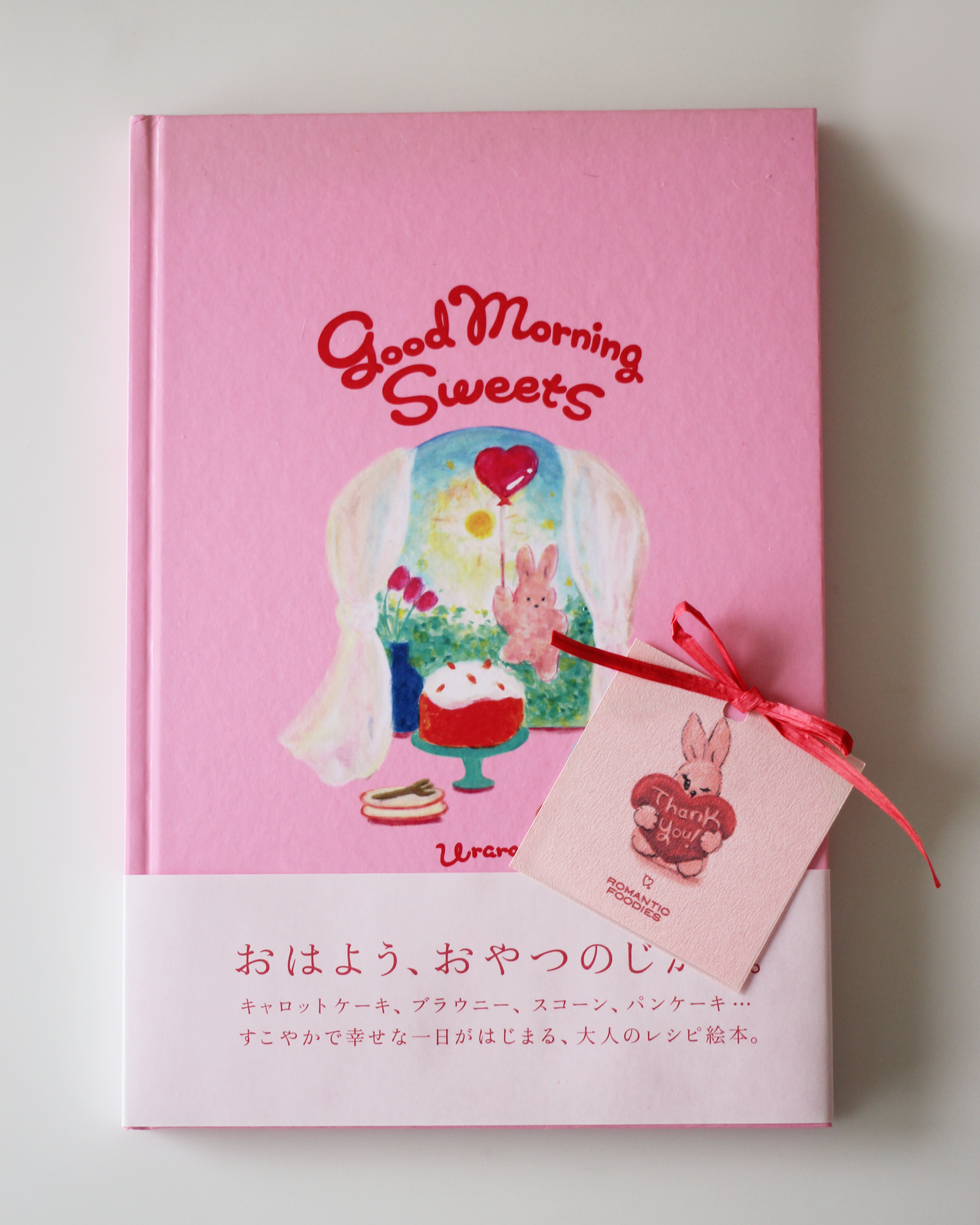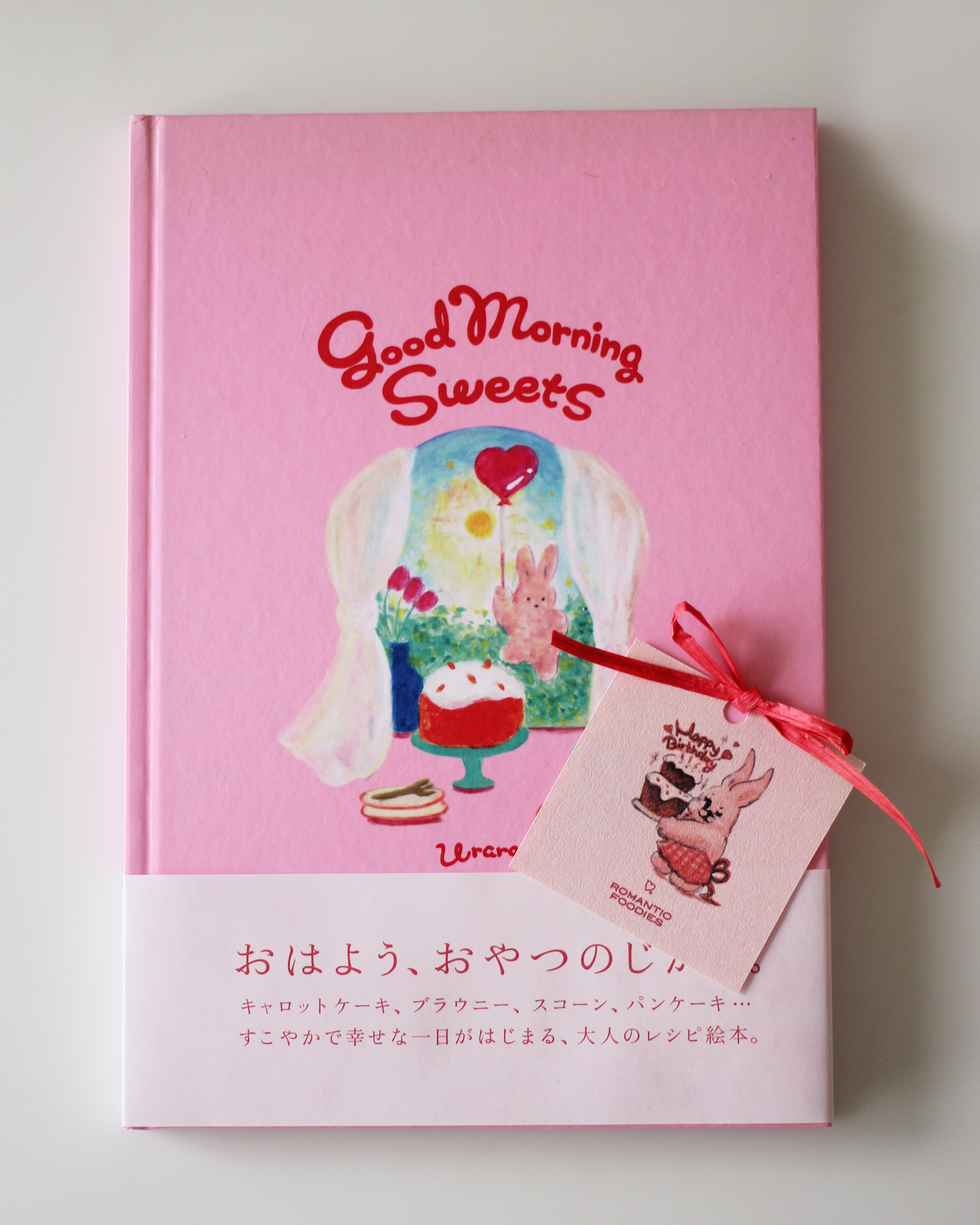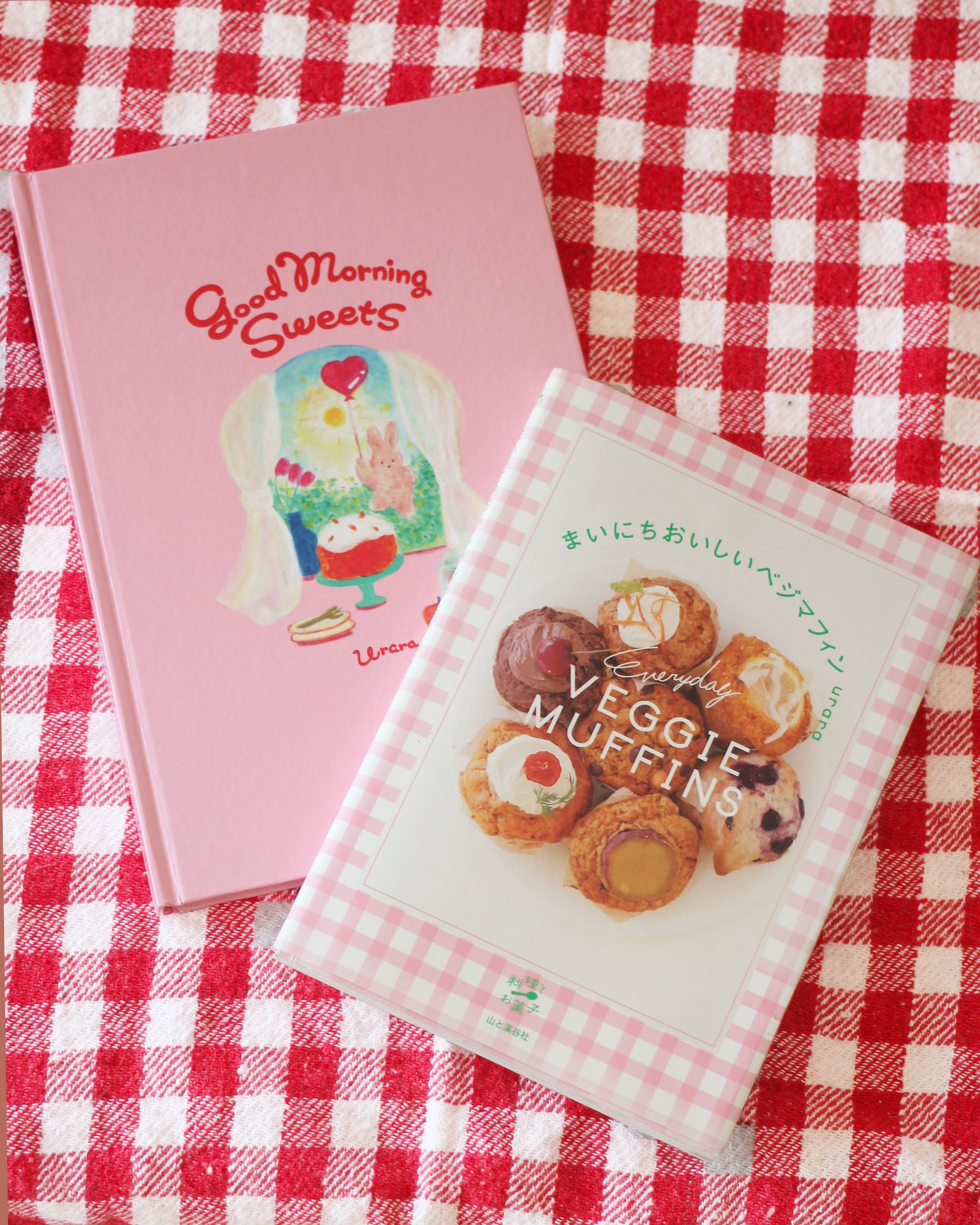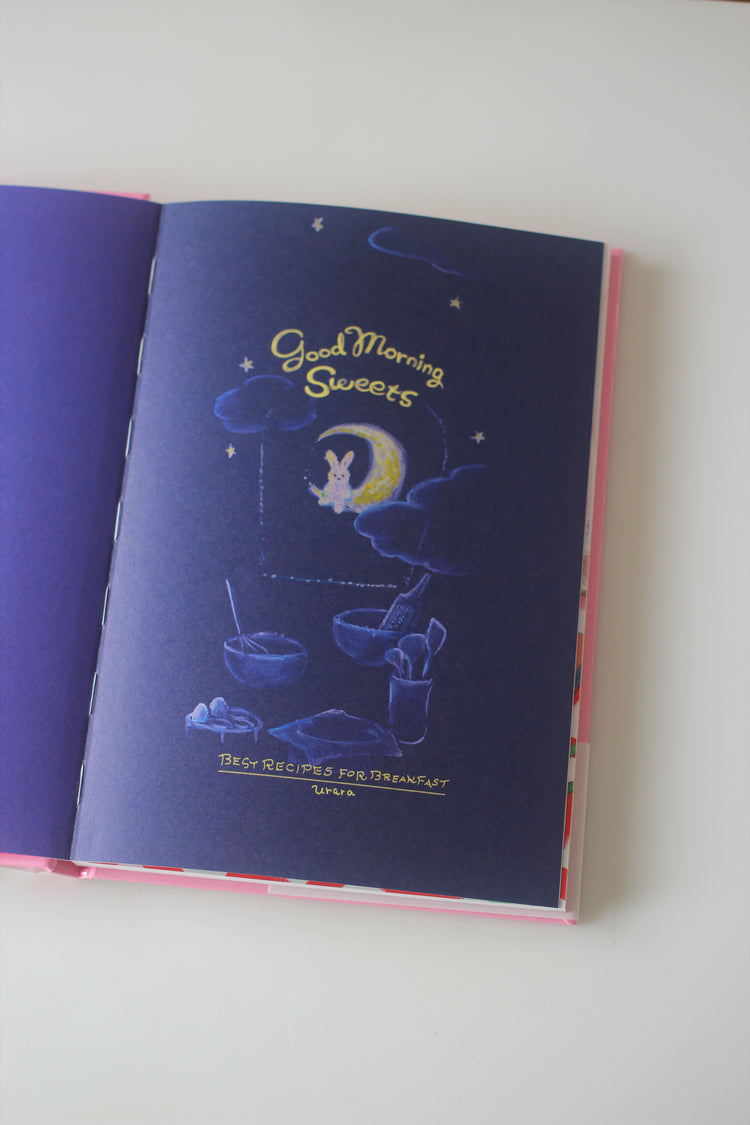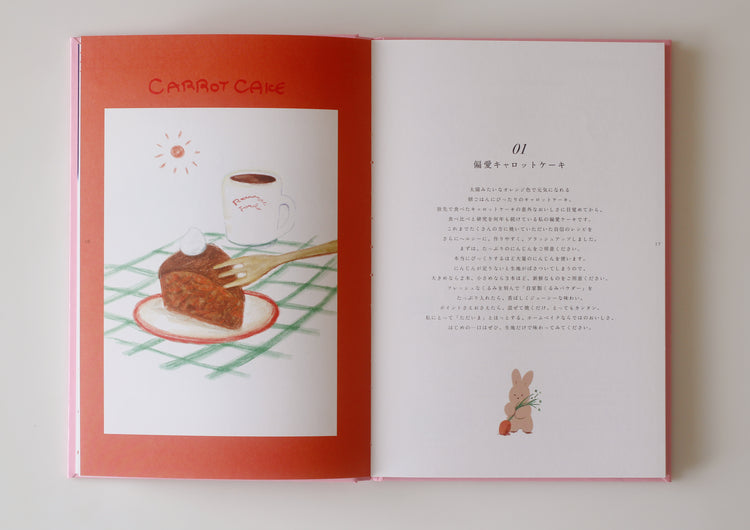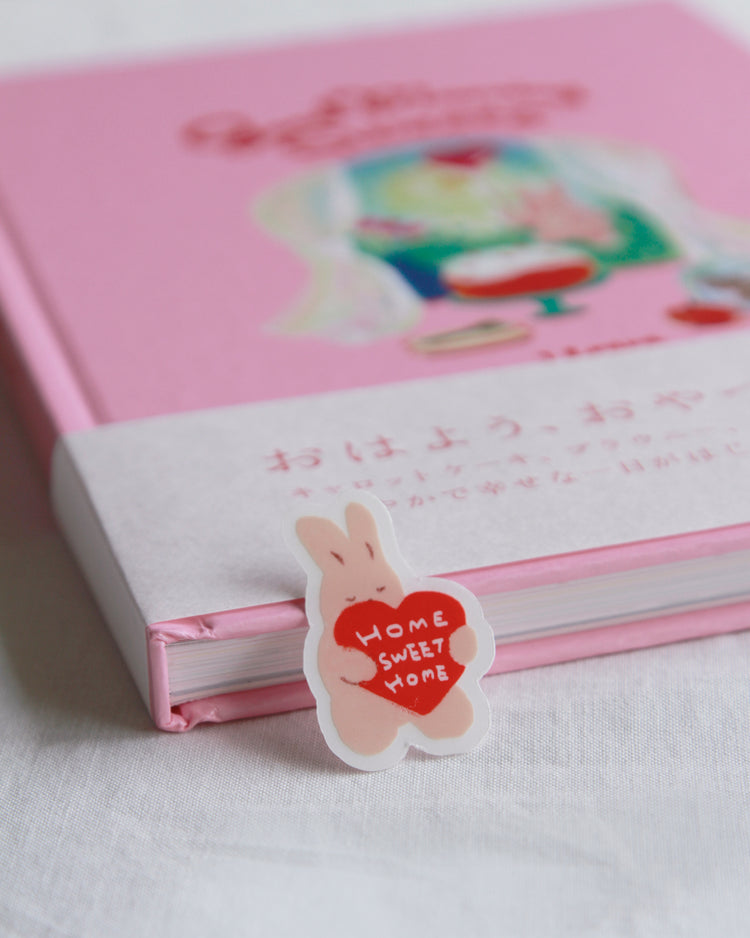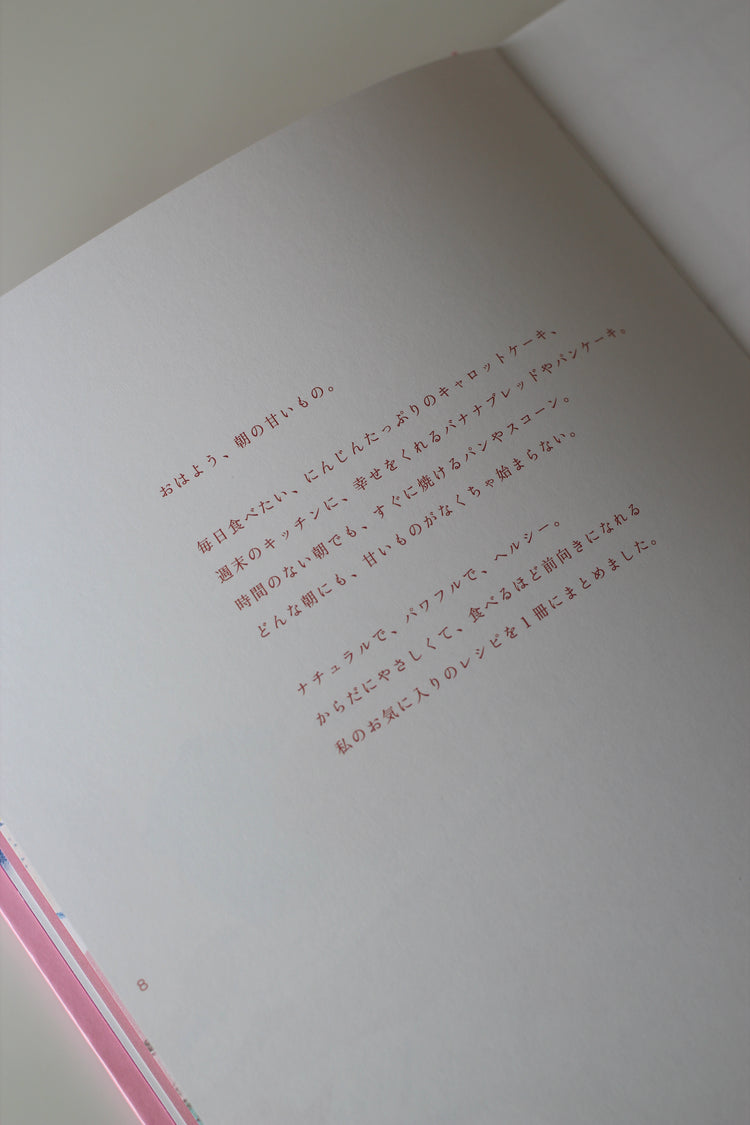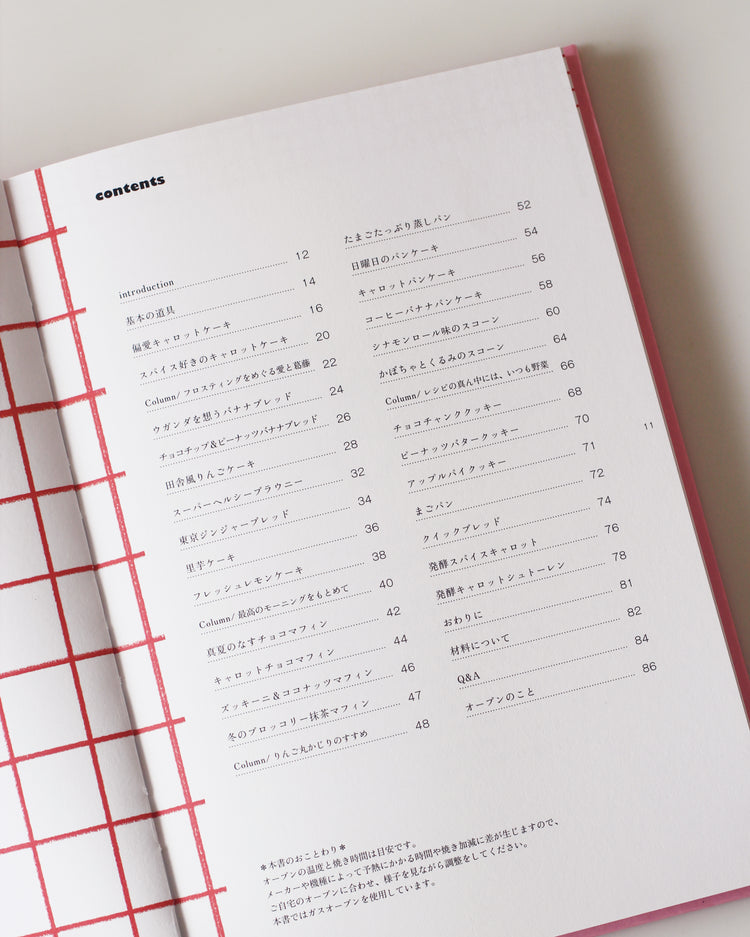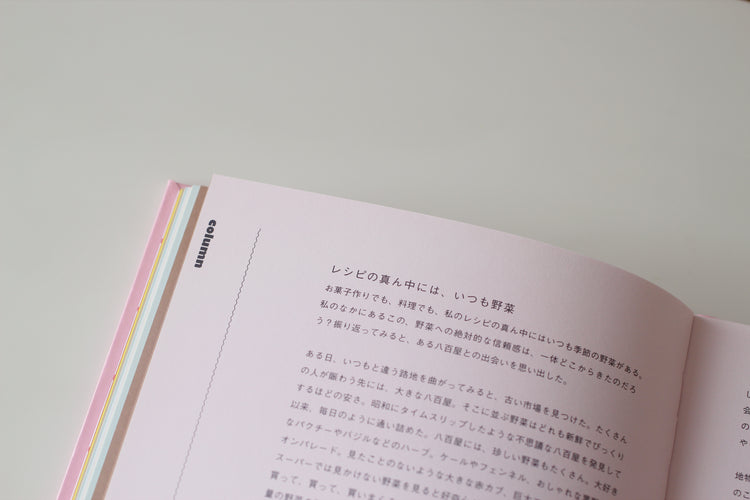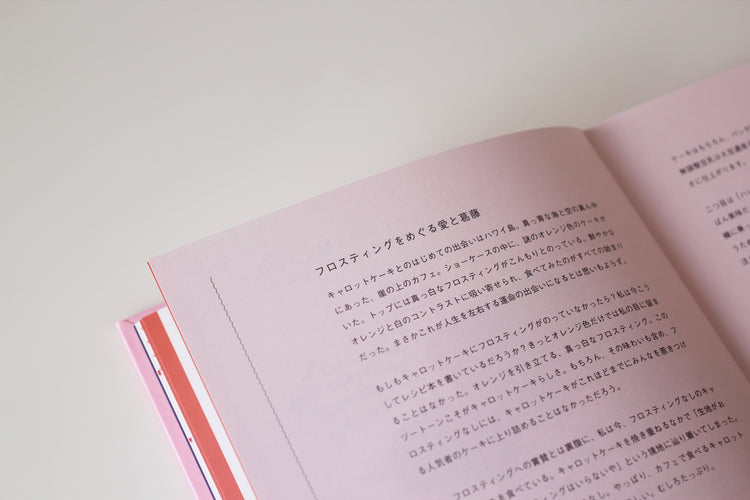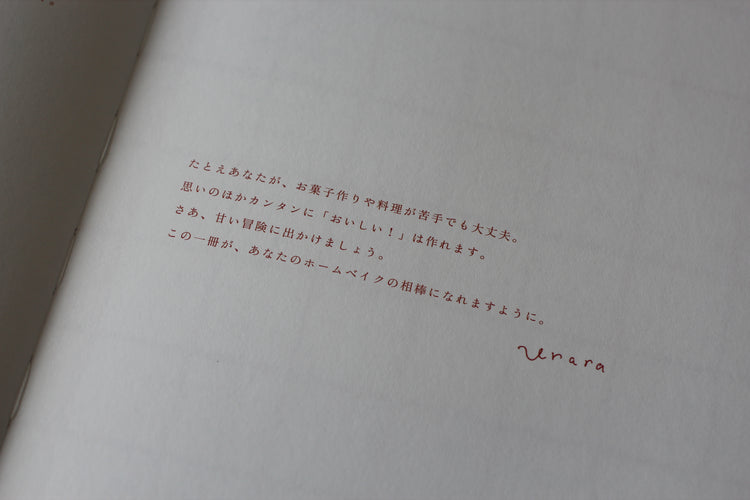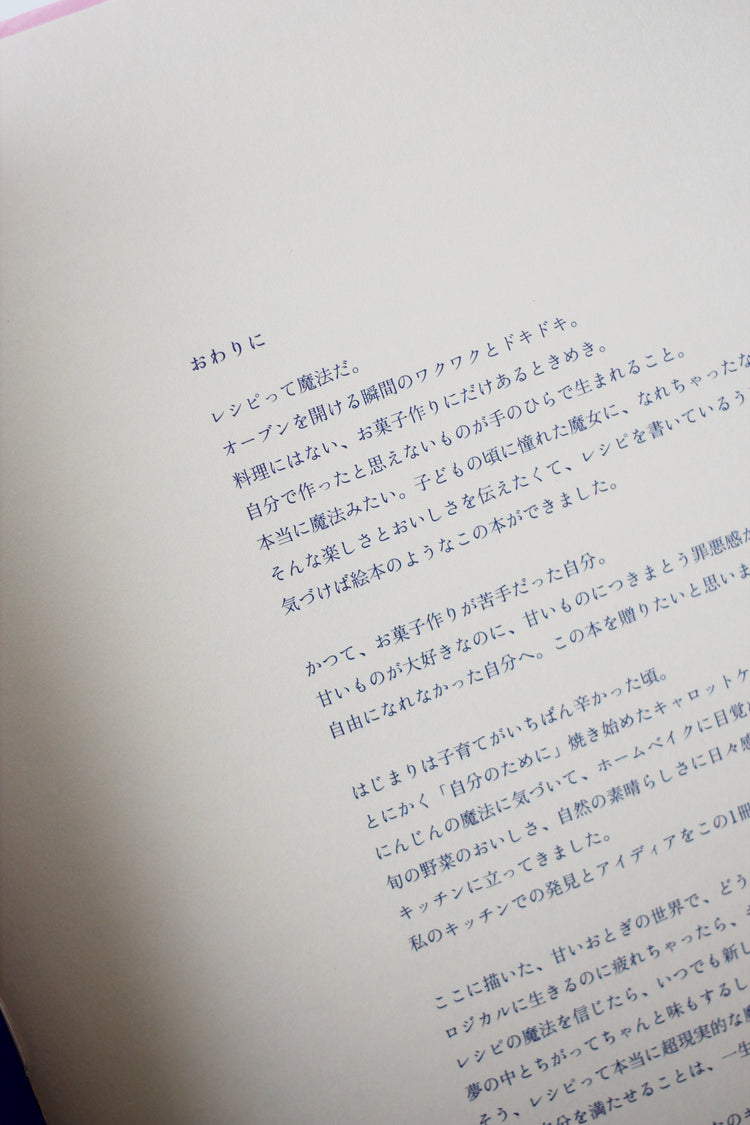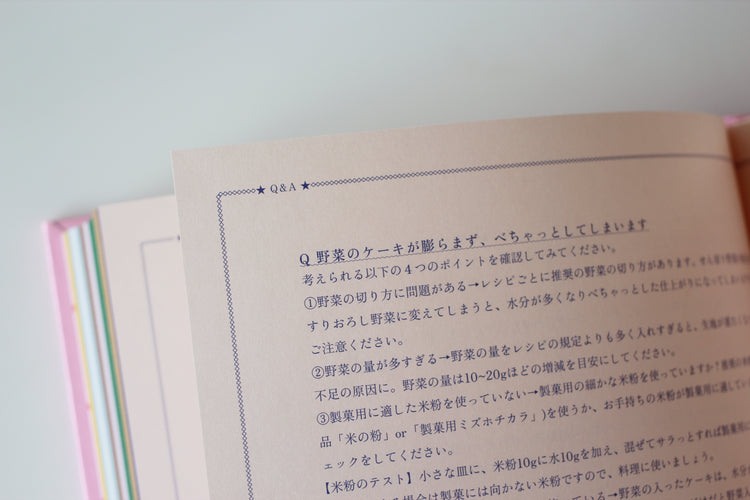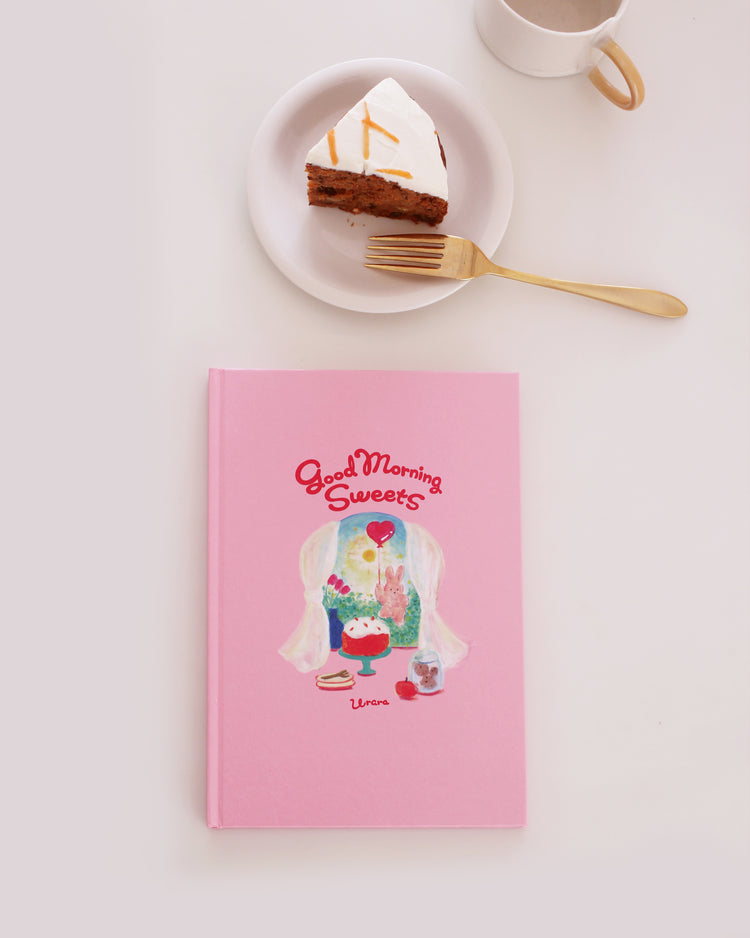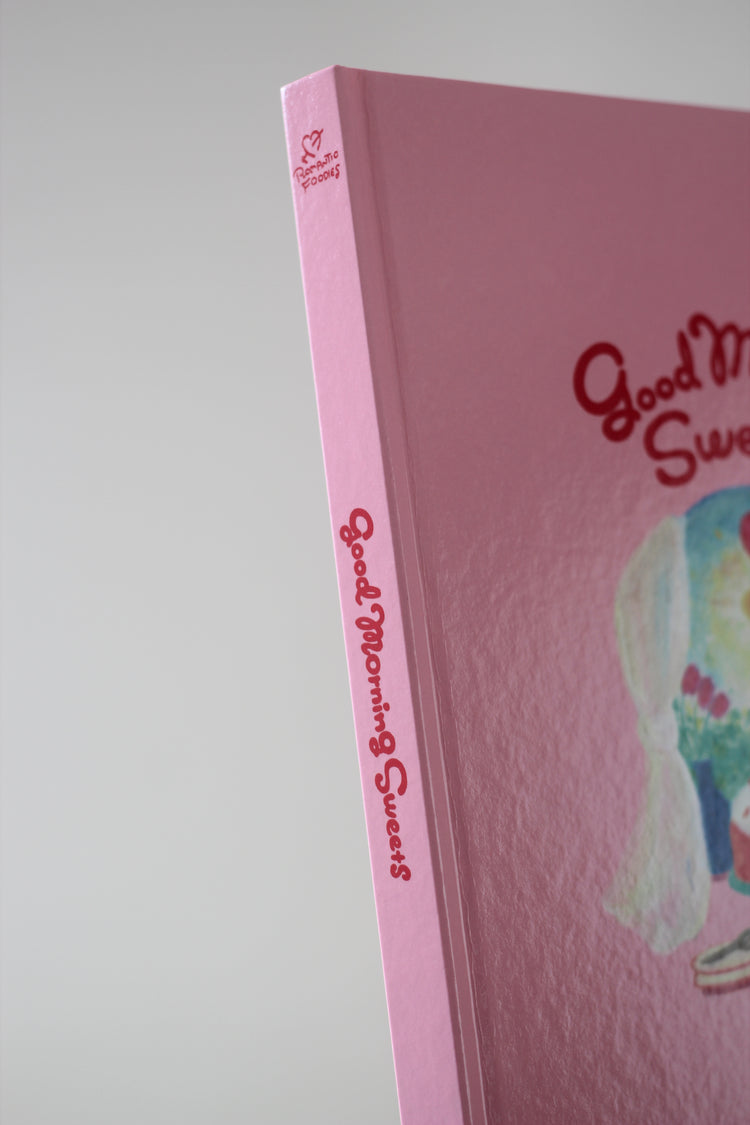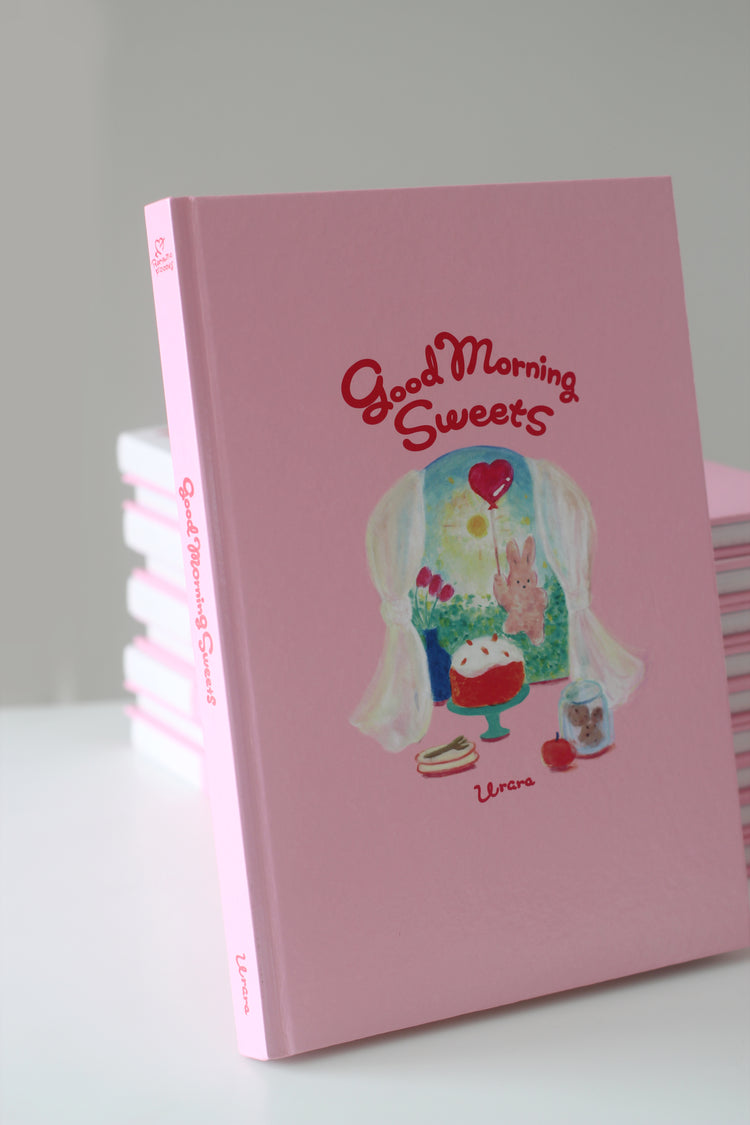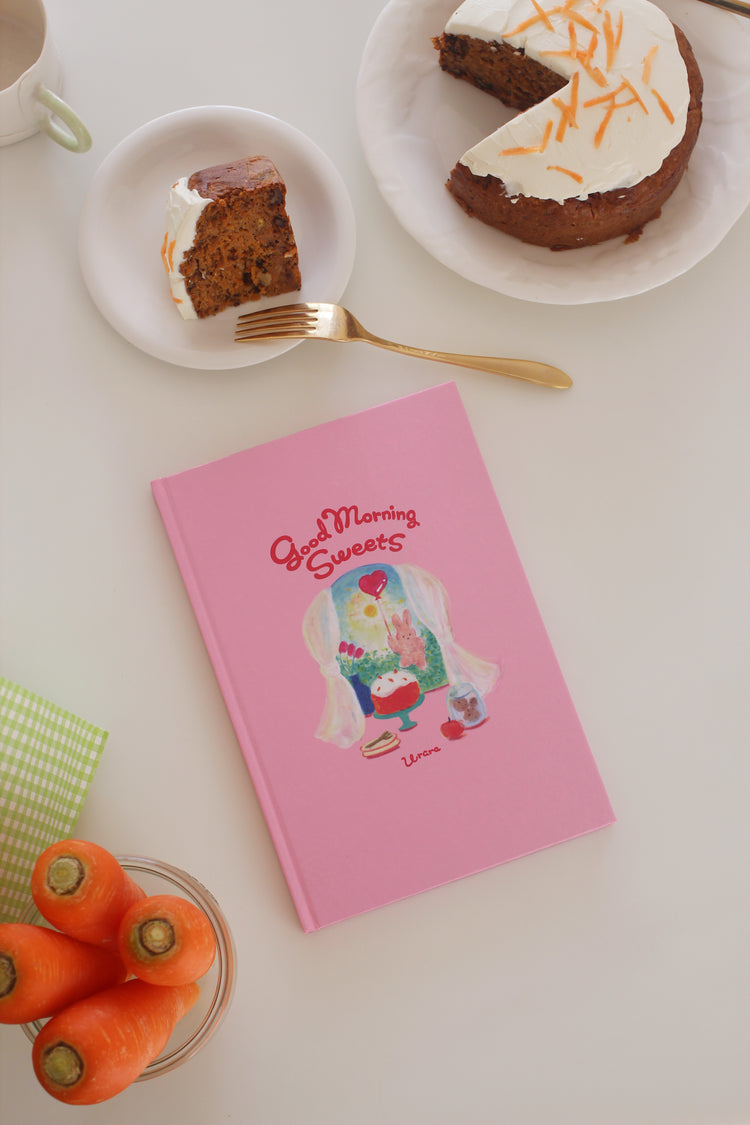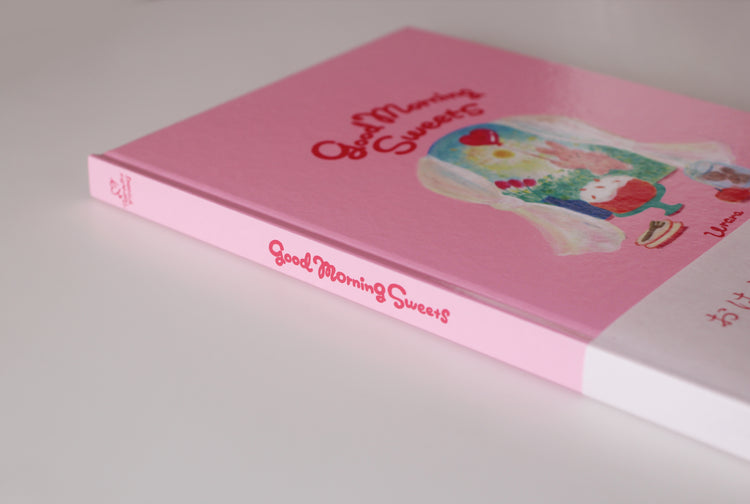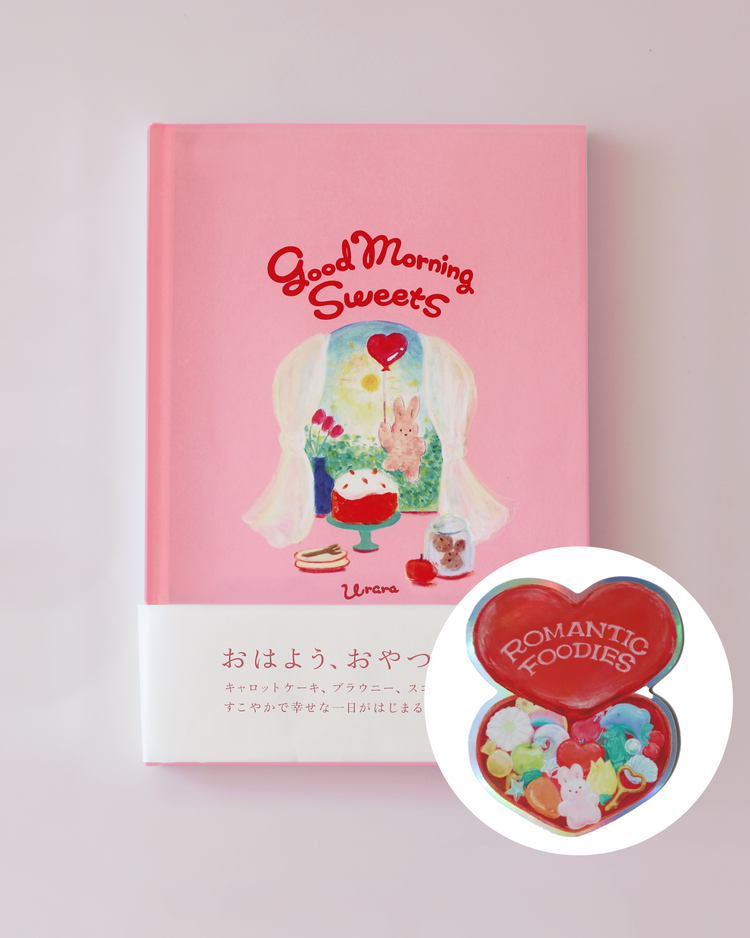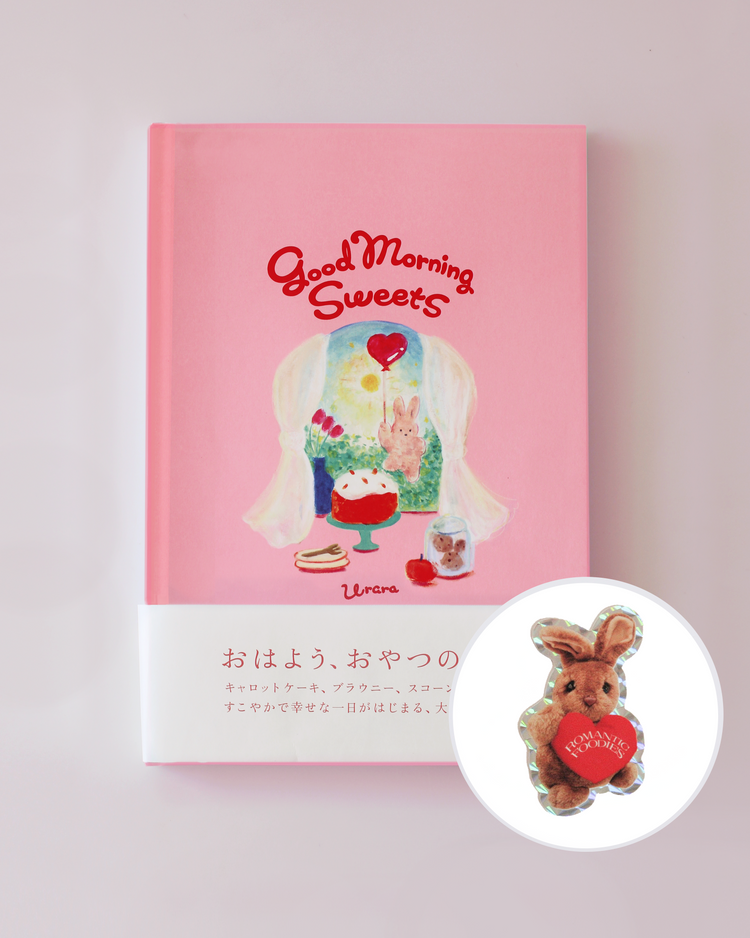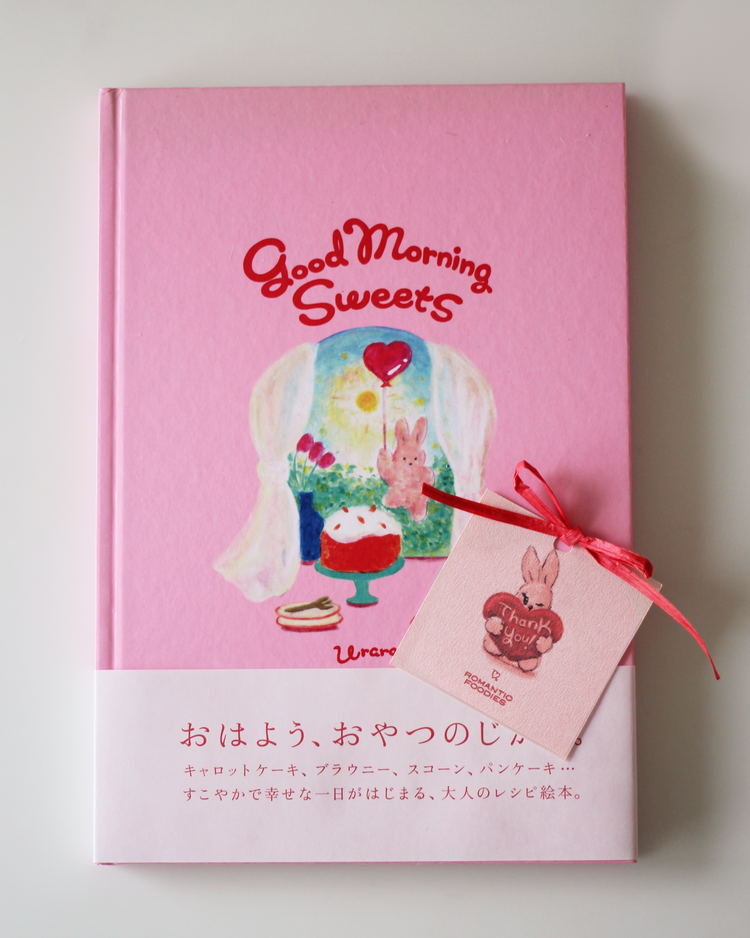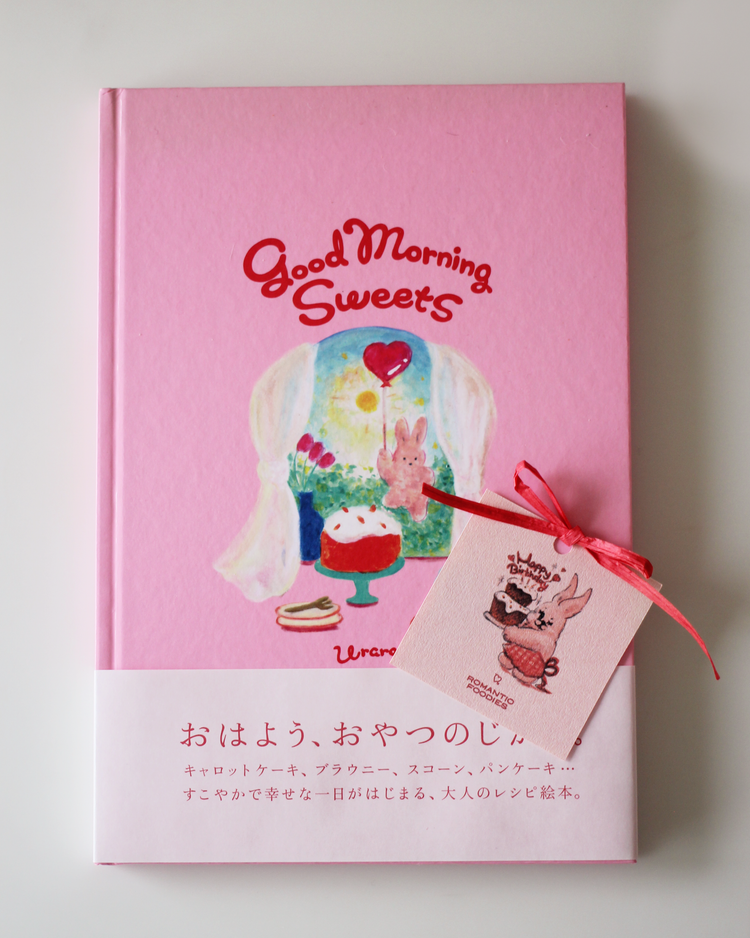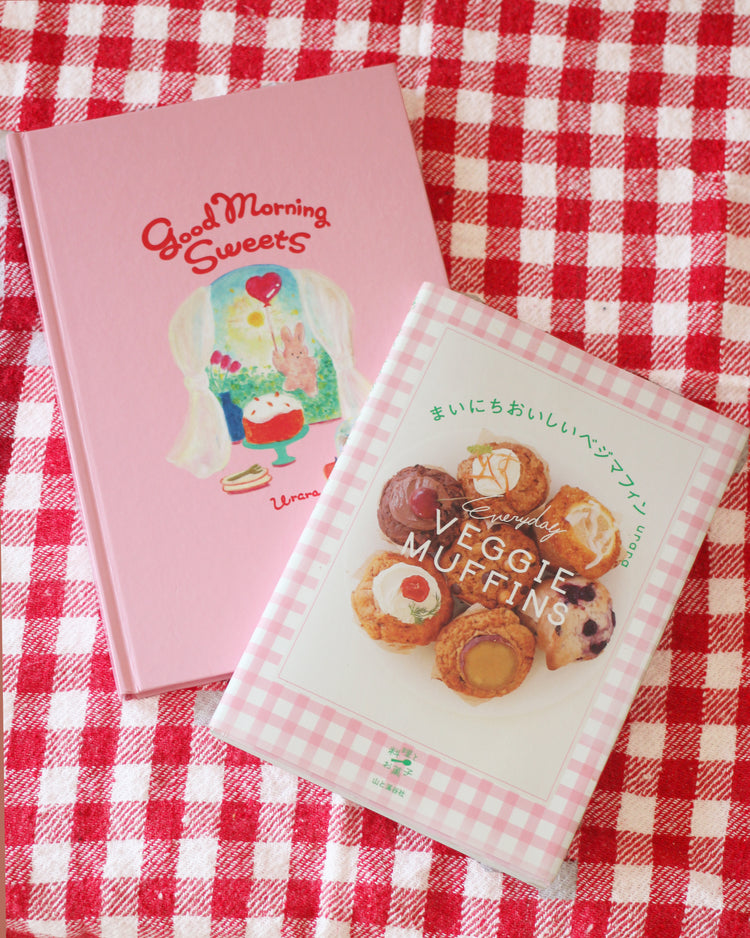杵と臼でつくからおいしい、最高のお餅のレシピ。

キャロットケーキに負けないくらい、餅が大好きのuraraです。「つきたてのお餅が食べたい!」の思いつきから、数年前に衝動買いした杵と石臼。田舎の家に三世代集まり餅つき大会をするのが年末の我が家の季節ごと。今年はやっと段取りやコツも身についてきたので、レシピを残します。来年の私へのメモも兼ねて。
STEP1 おいしい餅米を用意する

最高においしいお餅をつくりたい。だから餅米にもこだわりたい。今年は地物の松崎産のもち米をセレクト。伊豆は米所ではないけれど、実はお米がとってもおいしい。我が家は2升サイズの石臼なので、3キロが1回つくのにちょうどよい量です。
STEP2 前日の準備
①杵と臼を水につける

前日から杵を熱湯につけておきます。杵が乾燥していると、餅をついた時にピキっと杵が欠けてしまうことを防ぐことが理由です。
②餅米を水につける。

餅米は12時間以上、しっかり浸水させます。一晩、できれば12時間くらい。キッチンの涼しい場所で、温かい場所に置かないよう注意します。

しっかり餅米が水分を吸いました。
STEP3 餅つき当日の段取り
①蒸し器をセットする

蒸し器を沸騰させている間に、餅米をとぎます。

2キロの餅米は大量なので、何度かに分けて研ぎましょう。
蒸し器が沸騰したら、濡らした蒸し布を鍋にしき、餅米を入れます。

餅米は真ん中にくぼみができるように広げると、ムラなく蒸すことができます。

タイマーを55分にセットして、餅米を蒸します。
②臼を熱湯で温める。

蒸しあがる直前10分前に、臼に熱湯を張り、臼をしっかり温めておきます。餅米が冷えないようにすることが目的です。この熱湯は捨てずに、バケツに移し、合いの手の際の差し湯に使います。
②蒸し器でもち米を1時間ほど蒸す
1時間弱蒸したら、一度餅米を味見します。

芯まで柔らかくしっかりと蒸しあがっていたら蒸し上がり。

ツヤツヤぴかぴか!蒸し器ごと餅米を運び、ひっくり返して餅米を臼に入れます。やけどに気をつけて。でもここの工程をスムーズに行うことがおいしいお餅を作るポイントです。
③もち米をこねる。

すぐに「餅つき」をしたくなりますが、まずは「こね」。この「こね」を手早くスピーディーに行うことがおいしさの決め手。杵だけでなくしゃもじ、すりこぎを使い、3人で餅米をこねます。

杵に餅がくっつき出したら、さし湯をし、手で餅を返します。米の粒を感じなくなるまで、しっかりこねることがポイント。「こねは7割、つきは3割」といわれるほど、「こね」は大事な工程です。
④杵でつく。

餅米の粒感が見えなくなり、なめらかになったら、さあ、餅をつきましょう!杵を振り落とすときの重みをつかい、無駄な力を入れずにつくことがポイントです。とはいえ杵は重いので、筋力と体幹がない人には難しい!モタモタせずにスピーディーに行うことはおいしさのポイント。

餅が艶やかになり、のびがよくなれば完成です。

杵にくっつくくらい、びよーんと伸びます!

⑤餅を丸める

完成した餅をホーローバットに移します。
ぬるま湯で手を濡らし、餅をちぎります。

我が家のいちばん人気は磯部。醤油につけて、ノリで巻いてアツアツで召し上がれ。

おいしい海苔でまいて、パリっと。つきたてならではの柔らかなお餅は、やっぱり感動的なおいしさ。

私の大好物はきな粉餅。きな粉とお砂糖、塩をあらかじめふるいにかけておき、滑らかに。

大根おろしでさっぱりしたら、

あんこ餅!

あまい、しょっぱいの永遠ループ。今年もやっぱり食べすぎました。
保存について
食べきれないお餅は、冷凍補保存。餅があたたかいうちに丸めてます。餅取り粉を餅にふりかけ、手にもまぶしてくっつかないように行ます。でも、この作業が難しい。そのうえ大人もこどももみんなで作業するので、大きさもバラバラ。
元旦のお雑煮のぶんのお餅はは常温保存で。常温で保存すると固くなるので、弱火のグリルで軽くあぶってから、雑煮の汁の中で煮込めばふたたび柔らかく伸びの良いお餅になります。ただ、炊き立てのお米が時間が経つほど味が落ちるのとおなじで、出来立ての新鮮なうちに急速冷凍したほうがおいしいです。

来年はもっと上手になりたい。そして今年の反省は、用意した上新粉がザラっと舌触りが悪かったこと。来年は、無添加の餅とり粉を準備して望もう。量は1袋でOK。(いつも足りないと思うけど結局足りる)

見た目は多少不恰好でも、こどもから大人まで、家族みんなで、「おいしい!」の瞬間にむかって力を合わせて手作りする。そんな料理って、他にはなかなかないかも。1年ごとに細かくこのレシピもアップデートして、5年、10年、30年?と我が家ならではの餅つきレシピを高めていきたいと思います。来年も家族みんな元気にお餅をつけますように。良いお年を!urara